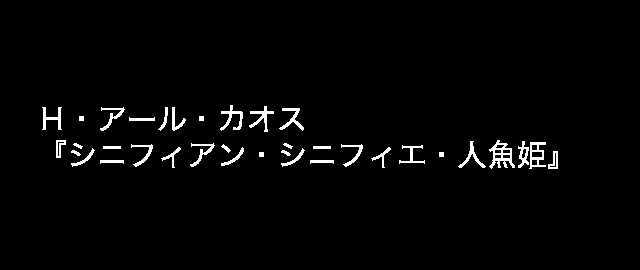身体の自然
振付家の中には二つの人格がある。演出家とダンサーと。演出家は観客を驚かす新しい形式を探り、ダンサーは自身の身体にこだわろうとする。最近は演出家的振付家の時代である。観客が新しい様式を喜んだからだ。しかし本当に良い舞台を生むためには両方が必要であるだろう。大島・白河の二人組は両者をバランスさせながら日本のモダンダンスとしては極めて高い水準の舞台を作り上げた。視覚的にも洗練されており、新作の音楽もいい。だがここでは身体に話を限ろう。
十五人のダンサーの動きには一時間半を飽きさせない工夫があり、所作の斬新を誇るフランスのヌーヴェル・ダンスと比べてもひけをとらない。だが注目すべきはその才気ではない。動きの工夫が身体そのものへの関心から切り離されていないことである。たとえばこのグループは以前からワイヤによる宙吊りを行う。しかしそれは『ピーターパン』のように重力を無視して空中浮遊するためではない。むしろ四肢の一部は床についている方が多い。ワイヤは五本目の四肢として体重の一部(あるいは殆ど)を支えるのである。たとえばふだんは二本の脚で支える身体を一本の脚と一本のワイヤで支えるというように。これは重力を無視するのではなく、ただ重力の身体への働き方を変えるだけだ。けれどもこれによってふだんはできない姿勢や動きが可能になる。身体は新たな制約と新たな自由を手にいれる。ダンサーの筋肉はいままで経験しなかった抵抗と速度と慣性がもたらす運動感覚に適応しなければならない。そして観客もまた、確かにその身体感覚を自分の肉体の中に感じとるのである。それは超人ピーターパンの雲を歩むような感じではなく、この人間的身体の可能性の拡張である。
作品のモチーフとなっているのはアンデルセンの『人魚姫』である。人魚の娘たちは十五歳になるまで海面に出ることを禁じられ、さまざまな噂に空想を膨らませながら誕生日の来るのを待っている。その日、初めて外界を見た人魚姫は、人間の王子に恋をしてしまう。魔女の計らいで彼女は声と引換えに人間になる。誰よりも美しい肢体と素晴らしい踊りの技も与えられる。ただし王子との結婚に失敗すれば彼女は泡となって消えねばならない。彼女は地上で王子と出会うけれども、思いを告げることができない。王子は他の王女と結婚する。人魚姫は泡になる。しかし舞台は原作をそのままなぞるわけではない。この童話は、女性の、そしてダンサーの身体の物語として読み替えられてゆくのである。
十五歳まで海中だけの生活を強制される人魚たちの閉塞感は、十八歳まで制服を強要される少女たちの被抑圧感として表される。外からは大人についての無数の情報に刺激され、内からは成熟した肉体の欲求に衝き動かされながら、彼女たちはセーラー服という拘束衣の中で禁欲するほかはない。ジュリエットが十四歳に満たなかったことを思えば、この抑圧は人間の生理に反しているだろう。本を投げ捨てセーラー服と格闘する少女たちの群舞は圧巻である。彼女たちは煩悶し、セーラー服を脱ごうとしては思いとどまる。やがてその中の一人がついに上着を脱ぎ捨てる。たちまち男が現れて彼女をさらってゆく。考えてみれば人魚姫とて、十五年の抑圧がなければ、海上に出た最初の日にたまたま見た男を恋するなどということは起こらなかったろう。人魚姫の悲劇は日本の少女たちにとって現在の問題でもある。
衝動的な恋は実らなかった。王子を殺せば生き延びられるが、人魚姫は自分の意志で剣を捨てる。彼女は月の光の下で自分の身体が泡になって消えるのを待つ。そしてひとり最後のダンスを踊る。人魚姫はいまや自分が完全に自由であるのを感ずる。このソロで白河直子は文字通り一糸も身に纏わなかった。制度的抑圧が制服による身体的抑圧として表現された以上、完全な自由は身体の完全な解放によって表現されるほかないからだ。もっとも現代日本の状況を考えればこれは戦略的に問題があろう。警察が目をつけるとか週刊誌が好奇の目で取り上げるとかいうのは、小さなことだ。観客の興味が別の所へ向くのではないかという危険である。確かに初めの一分くらいは私もヘアが気になった。しかしすぐにそれは関心から外れた。私は生まれて初めて「自然な身体」と対面しているような気がした。それは爪の先まで自由で透明だった。思えば隠すとは文化的行為である。それは社会のイデオロギーの反映であり、覆われた身体はすでに抑圧された文化的身体である。わざわざ覆いを取って見せることが売り物になるのも、覆うことが当たり前だというイデオロギーを前提にしている。だからストリップの裸体はやはり文化的身体である。しかし舞台にあったのは、一切の文化的制度から自由となった身体だった。いろいろな思惑を抜きに見れば、人間の身体は元来こんなに美しいものなのに、とこの舞台は教えていた。そして身体が自由を得るとき、それが踊りはじめるのはまた自然なことなのだとも告げていた。だがこのダンスが印象的な理由はそれだけではない。人魚姫はこの身体が間もなく泡になることを知っている。それは年齢的制約のあるダンサーの身体のはかなさでもあるだろう。自然な身体は滅びねばならない。だからこそ踊れるあいだは踊らねばならない。身体という恩恵に報いるために。薄明の中で踊るダンサーの姿は嵐の前の桜のように美しかった。