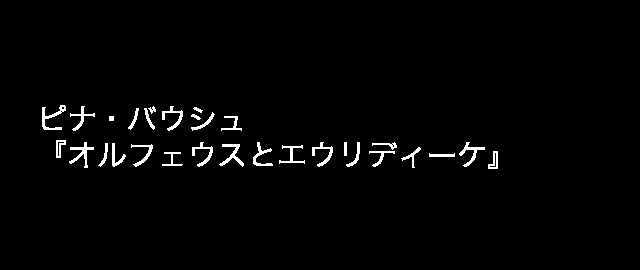悲劇の舞踊
二月下旬、パリ・オペラ座(ガルニエ)でピナ・バウシュ率いるヴッパタール・タンツテアターにより『オルフェウスとエウリディーケ』(一九七五)が再演された。ピナはいつも傷ついた者を扱ってきた。それはしばしば残酷さの表現と解されたけれども、彼女の眼差しはいつも傷つけられた側に向けられていた。この作品もまた愛ゆえの悲劇を主題としている。だが最近のピナを知る者にはこの舞台は異様に古典的であった。
西洋の伝統を遡れば、最も高級な芸術とされてきたのは詩である。そして古代に最も格の高い詩は悲劇であった。最古の芸術論といわれるアリストテレスの『詩学』が扱うのはもっぱらギリシア悲劇である。人に与える感動の力によって芸術の価値を計るなら、悲劇への敬意は当然であるだろう。
一方舞踊は芸術の中でも身分のいかがわしいものとされてきた。十八世紀にノヴェールがバレエの革新を志したとき、彼が試みたのはバレエを演劇に近づけることであった。即ち技巧の見せ物を切り捨て、全ての要素を劇的な物語の叙述に奉仕させることである。彼はギリシア悲劇のバレエ化によって成功を収め、「舞踊のシェイクスピア」と呼ばれた。
同じ頃グルックもオペラの改革を志した。彼の試みもまたオペラを演劇に近づけることであった。即ち歌手の技巧の見せ場を作るよりも、物語の構成を優先したのである。ギリシア神話に題材をとったその作品はオペラ史に期を画するものとなった。『オルフェオとエウリディーチェ』(独語版で『オルフェウスとエウリディーケ』)がそれである。
バレエが再び優美と技巧のショー的要素を強めたとき、ダンスの表現力を回復しようとしたマーサ・グラハムが採用したのもギリシア悲劇の舞踊化という道であった。このように芸術の改革がしばしばギリシアへの回帰という形をとるのは偶然ではない。もし、芸術は人の心を強く深く揺り動かすべきだという立場を選べば、ギリシア悲劇はその模範として西欧の伝統に屹立しているからである。
こうして、ドイツ表現主義舞踊の流れを汲みつつ、現代舞踊の改革者として登場したピナ・バウシュがギリシア神話を題材にとるのは殆ど必然のように見える。しかしノヴェールやグラハムの頃とは異なり、現代の舞踊家は二つの問題を避けることができない。一つは、舞踊が演劇の模倣をすることになお意味があるのかという問題である。言葉を持たない舞踊は物語の叙述に向いていない。だから童話風の単純なお話(ほとんどの古典バレ エ)か、既によく知られた筋書き(たとえばギリシア神話)に頼ることになる。細部は身振りで表すほかないが、説明的マイムはたいてい舞踊にとって弱点となる。だからこそ現代舞踊は抽象化への道を歩んできたのではなかったか。物語の叙述はむしろ舞踊本来の力を失わせるのではないか。第二に、舞踊のみならず文学・演劇・映画等においても問われていることだが、現代においていったい悲劇とは何かという問題がある。古代ギリシアの悲劇が現代になおリアリティを持ちうるだろうか。
ピナ・バウシュは、グルックのオペラを音楽に使うことによって第一の問題を解決する。物語は歌詞が叙述する。舞踊はひたすら情念の表現に専念すればよい。この二重構造は舞台の上にはっきりと提示される。なにしろ、主要な三人の登場人物は、それぞれ歌手と踊り手と二人一組で舞台に現れるのだ(ただし合唱はオーケストラ・ピットにあって、舞台上のコロスは皆踊り手)。しかもオルフェウスはアルトの女性歌手によって歌われるのだが、彼女は男装するわけではない。みかけ上はエウリディーケと区別のつかない黒のドレスである。観客は男性舞踊手をオルフェウスとして見ることはできるけれども、女装の女性歌手を同じように見ることはできない。ちょうど文楽の太夫からのように、ただ物語の劇的な叙述だけを受け取るのである。だが踊り手の方も、文楽の人形とは違い、微妙な芝居をするわけではない。つまり物語の写実的再現はしない。過酷な運命に耐えるとはどういうことか、愛に傷つくとはどういうことかの普遍的な表現である。それは物語がなくとも鑑賞に耐えるほど自立している。ただ物語というコンテクストを得るときその表現は いっそう痛切に立ち上がってくるであろう。また逆に物語の方もこの踊りによっていっそう深さを得るだろう。そういう関係である。
ピナ・バウシュはこの物語を四つの景に分け「哀悼」「暴力」「平和」「死」と名付けた。第一幕は初めの三景から成る。第一景はエウリディーケの墓前である。オルフェウスが妻の死を哀悼している。コロスもまた悲しみを歌い、踊る。この踊りが素晴らしい。コロスたちは螺旋に身をよじり、腕は捩じれて身に絡む。悲嘆の表現としてこれほど深く強いものを私は知らない(この身を揉む動きはピナの作品にしばしば現れるものだが、マ リー・ウィグマンを連想する人もいるかもしれない)。やがて愛の神アモールが現れて、オルフェウスに冥府から妻を連れ戻すことを許す。ただし地上に出るまで決して妻の顔を見ないという条件で。第二景は地獄である。屠殺者の風体をした三人の男性ダンサーが演ずる三頭の門衛は暴力のシンボルである。その彼らもオルフェウスのために冥府の門を開く。第三景は花咲く浄土である。エウリディーケは精霊たちと平和に暮らしている。そこへオルフェウスが現れ、二人は地上へと旅立つ。休憩。第二幕は地獄の道行である。第一幕のロバート・ウィルソンのように美しいセットは一掃され、三面を布壁に囲まれた抽象的な空間が広がる。二人の視線の関係のほか舞台には何もない。おそらくピナはこれをやりたかったに違いない。オルフェウスはエウリディーケを見ることができず、その理由を告げることも禁じられている。愛が深ければ深いほどその関係は残酷にならざるをえない。女は男を見つめる。危険を冒して地獄まで自分を迎えにきた男を。しかし男は女を見ない。懇願しても振り向かない。その訳も語らない。女は次第に不安になり、混乱してゆく。男はそれを手にとるように理解しながら、どうすることもできない。ただ耐えるしかない。女は絶望し、息も絶えそうになる。男は我慢できず、振り返る。たちまち女は死ぬ。自分の短慮が女を殺したと知り、男は後を追おうとする。原作のオペラでは、このあとアモールが現れて自殺を押しとどめ、エウリディーケを生き返らせてめでたしめでたしとなるのだが、ピナはとってつけたようなその部分を削除して悲劇として完結させた。これは彼女ならずとも、現代の演出家ならたいていそうするだろう。問題はこの幕が悲劇として十分に成功していないということである。振付が悪いわけではない。踊り手が下手なわけでもない。多分現代の肉体によって神話的悲劇を演じるという計画そのものに無理があるのだ。神話的悲劇は偉大であるけれども、現代の生活のなかではリアリティを持たない。現代の肉体は大袈裟な神話にはなじまない。先に述べた第二の問題はついに解決できなかったのである。おそらくそのことを一番感じていたのはピナ・バウシュ自身であろう。
この作品はピナのものとしてはごく初期の作品に属する。ほどなく彼女は神話も物語も自分の舞台から追放する。そして日常の中に見出された痛ましいもの、不条理なものを切取り、拡大して見せるようになる。それぞれに個性的なヴッパタールのダンサーたちは、水を得た魚のように、その肉体によって現代の悲劇を表現しはじめる。この方法を発見することによってピナ・バウシュは現代舞踊の改革者となり、ピナ・バウシュとなったのである。