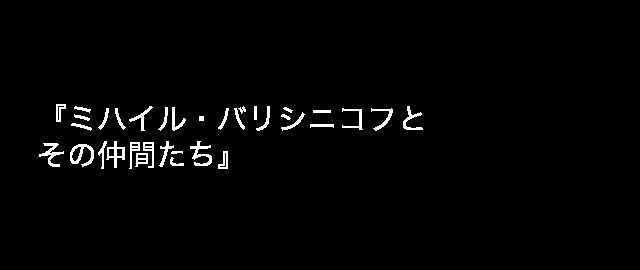クラシック、ちょっとクレイジー
バリシニコフは王子様だった。そのセクシーなタイツ姿はバレエ王国の納税者(ほとんど女性)の憧れであった。王子に肌を抱かれたい者のために「バリシニコフ・ボディウェア」が、抱かれたうえ汗をかきたい者のために「バリシニコフ・スポーツ」が売り出された(九二年度の売上予想は三千万ドル)。眼を閉じて酔いしれるために「ミーシャ」という名の香水が生まれ、そのショッピング・バッグには王子のけだるい顔が印刷された。だが王子にも悩みはあった。宮廷の舞踏会は豪華だけれど、同じことの繰り返しだということである。下町では庶民が屋台でおでんをつつき、焼酎のウーロン割りを飲み、ランバダを踊っている。人生の醍醐味はひょっとしたらあっちにあるんじゃないだろうか。王子は自由を求めて城を捨てた。
九〇年、マーク・モリスとともにホワイト・オーク・ダンス・プロジェクトを旗揚げしたバリシニコフは、ヨーロッパでのツァーを終え、今夏日本でその新しい活動のお披露目をした。そのプログラムは、座付き振付家であるモリスの作品が四つ、そしてバランシン、マーサ・グラハム、ポール・テイラー、デヴィッド・ゴードン、ラー・ルボヴィッチなどの名前が並ぶ。バランシンの外はみなモダンダンスの作家である。そのバランシンの 『エピソードより変奏曲作品三〇』も、彼がマース・カニングハムの先輩であることを思い出させはするが、ロシア・バレエの末子であることを忘れさせるような作品である。集められた十三人のダンサーも、主にモダンダンスでキャリアを積んだ連中である。ではバリシニコフはバレエを捨ててモダンダンスに身を投じたのか。実際多くの人がそう考え、そう問うたらしい。そこでバリシニコフとモリスは共にバレエとモダンの区別が無意味であることを強調する。「ダンスにバレエもモダンもない。よいダンスと悪いダンスがあるだけだ」と。もちろん現実にはバレエとモダンはあり、その基本テクニックも違う(バリシニコフ自身、バレエよりモダンの方が自分の身体にはつらいと語っている)。ただ舞踊界の前線ではバレエとモダンの境界が急速にぼやけつつあるのも確かである。その最先端にたとえばトワイラ・サープとモリスがいる。もっともこの二人のやり方は違う。サープはバレエを基本に語彙を拡大して新しい舞踊言語を再編成しようとしている。一方モリスはバレエもモダンもそれ以外のものも、ほとんど無頓着なまでにいっしょくたに投げ込み、外側から一定の枠組みを与えることで無理やりダンスにまとめてしまう。おそらくバリシニコフは、あらゆる技法や動きをダンスの名のもとにとりこむ、このモリスの才気に魅かれたのであろう。なぜなら、バリシニコフもまた、ありとあらゆる技法と動きをダンスの名のもとに演じてみたいからである。今回のプログラムも十分に幅が広い。半世紀前の『エル・ペニエンテ』は苦行者の苦悩と歓喜を表すいかにもグラハムらしい心理舞踊であり、ゴードンの『パンチとジュディ』は下ネタをも辞さない笑劇であり、ルボヴィッチの『日の出を待ちながら』はブロードウェイでもやれそうな軽いエンタテイメントである。そのいずれをもバリシニコフは嬉々として演じている。
モリスとバリシニコフの出会いの意味は、Bプログラムの中の二つの作品、『カノン形式のワルツとエチュード』及び『十の提案』によく表れている。九人で踊られる前者はカノン形式の音楽に合わせてさまざまな動きの型が展開され反復されるものだが、その中には、常識的にはとうていダンスに使えないだらしない動きが含まれている。だがそんな動きも、何人かが同時に行ったり、明確なリズムで反復されたりすると、立派にダンスに見えてくる。逆に言えば、時間的秩序と空間的構成が眼に見えて明確なら、動きの型そのものは何でもありというわけだ。モリスは優美から珍妙まで、流麗から無骨まで、あらゆる動きの型をダンサーに課す。その型をどうこなすかはダンサーの側の問題である。とりとめのない動作に表情をつけ、ばらばらの型に一貫した質を与え、全体として意味のある動きに仕立て上げる。この点でバリシニコフは9人のダンサーの中で群を抜いている。モリスからみれば振付の解釈に優れている。観客からみればどんな動きも面白くみせてしまう「うまさ」を持っている。このうまさがさらに発揮されるのはソロの『十の提案』である。ピンクのパジャマを着たバリシニコフは無邪気な子供のようである。身体を動かして遊ぶことが楽しくて仕方がないのだ。初めは自分の身体だけで、やがてフラフープの輪や椅子やリボンを見つけ、それらと猫のように戯れる。教科書どおりにしか踊れないダンサーがこれをやれば、きっと退屈なものになるだろう。バリシニコフはさりげない動きに表情を与え、味を出し、魅力的なダンスに仕立ててしまう。いやあ、うまい。しかしこの「うまさ」はしだいにくどく思えてくる。あらゆる動きが同じバリシニコフ風の味付けになってしまうからだ。味の素をかければ何でもうまくはなるけれども、みんなグルタミン酸の 「うまみ」になってしまうように。もちろんこれを悪いとは言えない。満場の納税者は、これをクラシック・バレエの血がもたらす王子の芸として愛しているのだから。彼女たちにとって、バリシニコフは、時々やんちゃに羽目を外すけれども、やはり血は争えぬ王子様なのである。
「ミーシャ」の成功に味をしめたのか、最近男性用香水「バリシニコフ・プー・オム」が発売された。広報資料によれば、その香りは「クラシック、けれども少しクレージー」であるという