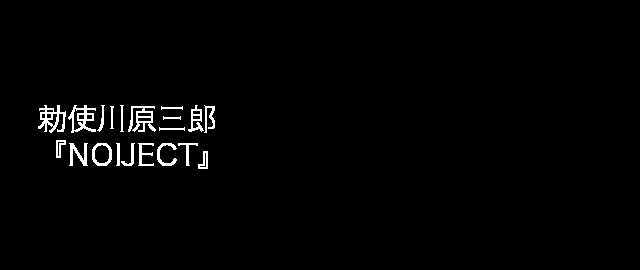ノイズとしてのダンス・オブジェとしてのダンス
『ノイジェクト』横浜公演は一つの事件として記念されるだろう。ついに勅使川原三郎がその様式を完成したからである。誰もが知るとおり、彼はこれまでにも個性的な手法をいくつも開発してきた。だが手法をいくら蓄積しても様式に至るわけではない。彼の意志と想像力が、多くの有能な作家の越えられぬ一線を越えたのである。
一個の様式とは独自の美意識あるいは独自の芸術観を基礎として立つ一つの完結した世界である。たとえばクラシック・バレエや歌舞伎はそれぞれ首尾一貫した様式をもつ。両者は互いに相手の型を取り込むことはできない。基礎となる美意識の性質が違うからである。手法や型を思いつくのは多少の才があればできるが、様式を創りだすのは難しい。それはいわば一個の宇宙をつくることだからである。舞台の上では勅使川原のこれまでに開発した手法がいくつも使われた。だがそれらはもはや「個性的な手法」として眼に立つことはなく、全体の中に所を得て、新たな舞踊の宇宙を現出させるのに奉仕していた。新奇な要素が全て必然性をもって見えるとき、新しい様式は完成したと言いうるのである。
夜七時、横浜市内の集合場所に集められた観客は、窓を塞がれたバスに拉致される。降ろされた場所は、体育館を四つつなげたほどの大倉庫である。間延びした空間を仕切るように裸電球を懸けた鉄板の列がカーテンのように吊るされ、自動車の金属ホィールが床に並ぶ。観客はここで暫く待たされる。薄暗い空間をうごめく人々のシルエットはマネキンのようにみえる。やがて鉄パイプの階段席に導かれ、闇を見つめる。目が慣れてくると、眼前の巨大な金槌のような鉄柱と、背後と左側面を鉄の壁に遮られた鉄の床が見えてくる。大音響が響きわたり、黒装束の人の群れが闇の中から湧き上がり、整然と奇妙な動作を始める。音はノイズとしか言いようがない。メロディーもリズムもなく、特定の音色さえない。巨大な空間に広がる鉄のインスタレーションは舞台美術というよりオブジェである。そしてダンスもまた、通常の意味でのダンスとは言いにくい。この動く身体とダンスとの関係は、ちょうどノイズと音楽、オブジェと美術の関係に等しい。いわばノイズとしてのダンス、オブジェとしてのダンスなのである。ノイズとは何の音か特定できない音である。オブジェとは何の役に立つのか何を表現しているのか特定できない人工物である。いずれも日常的な意味のシステムでは捉えられない音や物体である。この身体の動きもまた、これまでの動作や舞踊のシステムでは捉えることができない。動きは何の意味も感情も表さず、多くの舞踊ファンを陶酔に誘う優美や躍動もここにはない。といって何でもない動作では決してない。ここで鳴り響くノイズが、都市で聞き慣れた環境騒音とは異なり、その音の強さと鋭さによって人為性を強調し、環境に屹立しているように、このダンスもその動きの人為性と強さと鋭さによって屹立し、何でもない動作とははっきり区別される。このようなダンスは異様な存在と出会う緊張をもたらすが、決して陶酔をあたえない。ちょうどオブジェが物質との異様な出会いを仕組むものであるように。
もともと勅使川原のダンスは無機質である。手足の型の問題ではなく、動きの質そのものに表情がない。バレエやモダンダンスの様式の中でなら、「ダンスじゃなくて体操だ」と嫌われるだろう。しかしここでは無機質であることが意義をもってくる。様式が完成するとき、動きや装置や照明などこれまで彼の好みないし個性と思われていたものが、全て必然性を持ち始めるのである。勅使川原のソロは錆びた鉄材の中で研ぎ上げられた刃物のように光る(彼の振付に無理に表情をつけて踊るダンサーは、鉄材の中の古着のように見えて却ってみじめである)。彼の身体はそれ自体刺激的なノイズとなり強靱なオブジェとなる。舞台はさまざまのノイズ(そしてオブジェ)が設置され、作り出される場所となる(この性格は、ダンサーのレバー操作に応じて稲妻のように明滅する照明、ダンサーの靴に仕掛けられたマイクの拾うノイズなどによっても強調される)。
ダンスらしくない動きによるダンスの試みはこれまでにも(とりわけアメリカに)あった。日常的動作を取り入れたり、機械的な、動きのための動きを演じたり。だがそれらには独自の芸術観はあっても(実はそれさえ少ないが)、独自の美意識はなく、おおむね退屈な実験にとどまった。しかし勅使川原の様式には確かに美意識がある。それが彼の舞台を感動的なものにしているのである。
帰りの電車で劇評家の友人が、演劇を含めてこの一年半に見た舞台の中で一番感動したと言ったあと、こうしみじみと続けた。「勅使川原と同じくらいキャリアのある劇団は沢山あるのに、どうしてこんなに差がついちゃったんだろう」。私は答えた。「志が違うんじゃないの」