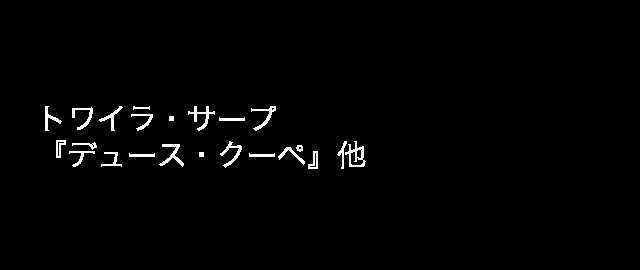トワイラ・サープの手法とスタイル
この二十年余り常にアメリカ舞踊界の最先端に位置づけられてきたトワイラ・サープの作品が東京で立て続けに上演された。パリ・オペラ座バレエ団による『プッシュ・カムズ・トゥ・ショーブ』、そしてサープ自身の舞踊団による三つのプログラムの上演である。旧作からは、一夜にしてサープを有名にしたといわれる『デュース・クーペ』、正装したカップルたちがシナトラの歌に合わせて優雅に社交ダンスを踊る『ナイン・シナトラ・ソングス』、めくるめくダイナミズムとスピードで「最良のアメリカン・ダンスを見たければ『ゴールデン・セクション』を見ろ」(オブザーバー紙)とまでいわれた『ゴールデン・セクション』など。そして四つの最新作。このサープの回顧展は、かつて「才気を鼻にかけている」とか「偶像破壊者」と呼ばれた異端児がどのようにして自身の手法を確立し、大家になりおおせたかを見せてくれた。
六〇年代の半ばに振付家として出発したとき、サープは従来のダンス領域を逸脱する実験的グループ(ポスト・モダンダンス)の一人だった。その試みには、当時の前衛美術であったミニマル・アートやコンセプチュアル・アートに通じるものがある。しかしサープはこの頃の作品を再演しない。多分その価値がないと考えているのだろう。今回のプログラムで一番古いものは一九七三年ジョフリー・バレエ団のために振り付けた『デュース・クーペ』である。当時バレエ団がモダンダンスの舞踊家に振付を依頼するのはあまり例のない冒険だった。ましてポスト・モダンダンスと言えば、ふつうの観客には難解・退屈ということになっている。ところが『デュース・クーペ』は成功した。余りの評判に、六回上演の予定を十回に増やしたほどである。誰が見ても面白かったのだ。舞台の奥では、日頃ニューヨークの地下鉄に落書きをしている十代の少年たちが特に雇われて背景幕に落書きをしている。スピーカーからは、六十年代西海岸風俗を代表するビーチボーイズの脳天気な歌が響く。白いチュチュをつけた一人のバレリーナがバレエの基本を繰り返し稽古している。そのまわりを、二十人の若者が、ある時はバレエっぽい、あるときは全く非バレエ的な動きでポップな風俗を表現する(たとえばマリファナの回し飲み)。ダンスのボ キャブラリーからみれば、バレエでもあり、モダンダンスでもあった。しかし作品全体のスタイルとしては、どちらでもなかった。サープ自身、この成功によってその後の方向を掴んだようである。
『デュース・クーペ』は初演当時から、一種のきわものであって繰り返し上演に耐えるかについては疑念を呈する批評家もいた。二年後の『デュース・クーペⅡ』に対しマーシア・シーゲルは初演の面影も辛うじてあるといった冷たい評をしている。ましてほぼ二十年を経た今回の『デュース・クーペⅣ』が初演の面影をどの程度とどめているのかは分からない(少なくともダンサーの数は少ないし、落書きは初めから出来上がったものをぶら下げているだけだ)。もちろん一人のバレリーナと若者たちという基本構図は変わらない。しかし舞台の上に繰り広げられるものの印象は、若者の風俗というより、バレエと非バレエの動きを違和感なくつなごうとする構造的な努力である。
この印象は『ナイン・シナトラ・ソングス』ではより明確になる。かつてバリシニコフが踊った『シナトラ・ソングス』のビデオを見ると、社交ダンスというものがもつ文化的イメージ、即ち洗練・優雅・セクシー・愛といったイメージをことさら大袈裟に提示して、笑わせる。ダンサーたちは、くさいダンスのくささを自覚しつつ、ことさらにくさくやってみせている(この自己批評的手法は『プッシュ・カムズ・トゥ・ショーブ』ではより複雑な形で採用され、抱腹絶倒の効果をもたらした)。しかし今回の『ナイン・シナトラ・ソングス』を観客はだれも笑わない。いや笑えない。ダンサーたちがひたすら大まじめであるからだ。彼らは自分の動きがくさいものであることを自覚していない。むしろ優雅であり、セクシーであると思っている。たぶん高度な技術を要することだけは自覚している。こうして作品は複雑な技巧と機知にあふれた出来のよい社交ダンスとして提示される。観客は、たしかに出来がよいことを認めざるをえない。しかし同時に、ブロードウェイのダンス(たとえば『グランド・ホテル』でムードを盛り上げるために使われた大袈裟なだけのデュオ)のようにいささか退屈であることも否めないのだ。
だがこれはサープの方針であるらしい。聞くところでは、彼女の現在の関心は、バレエとモダンダンスの垣根を取り払い、包括的なダンスのシステムを構築することにあるという。そして彼女の新作は、『メンズ・ピース』を除き、まさにそのような作品である。バレエをはじめ様々なダンスのボキャブラリーが引用され、変形され、継ぎはぎされる。引用の単位は断片である。語の引用はあるが句の引用はない。そのため、ある動きがたとえばバレエの特徴を見せることはあっても、一連の動きがバレエのスタイルをもつことはない。スタイルとは言わば美意識の型である。クラシック・バレエにせよ歌舞伎にせよ表現の理想についての明確な美意識があり、それに基づいて全ての動きの語彙と文法が作られている。観客もまたこのスタイルに応じた予期と身構えをもって舞台を見る。そしてこの身構えがあればこそ、流れる動きについてゆくことができるのである。どれほど突然の動きでも、それが用意された美意識の枠内にあるかぎり、その表現を把握することはできる。ところがサープ式の継ぎはぎはこの身構えを混乱させる。観客は次々と転変する動きを捉えるのが容易でない。ここにサープの特徴としてしばしば言われる、不統一・複雑・せわしなさなどの印象が生まれる。今回の新作群は、多様な動きの複雑な接合と巧緻な構成によって、サープ式ダンスの特徴をくっきりと打ち出している。しかしそこにはスタイルというものがない。そしてサープ舞踊団の公演作品の多くが、最初の数分こそ面白いものの、次第に退屈を感じさせたのは、おそらくこのスタイルの欠如にある。多分私たちは、何の身構えも取ることができないまま長時間何かに注意を注ぐことが生理的に難しいのである。
しかしかつてのサープにはスタイルがあったように思う。それは動きについての美意識ではないが、過去の文化や舞踊の遺産を引用するときの手付きにみられた、暖かい皮肉、肯定的な自嘲といった態度である。この身構えをサープは全く失ったわけではない。『メンズ・ピース』でひさびさに舞台に立ったサープはダンスについてユーモアたっぷりに話し、踊る。これはいわば彼女の自伝的エッセイである。その基本的態度は昔と変わりがない。しかしこの態度は露骨に言葉によって語られ、ダンスによって解説されるのであって、昔のようにダンスのスタイルとして表れてくるわけではない。あえて言えばこれはダンスについてのコントであって、ダンス作品ではない。そしてこの作品以外からは、サープはこの態度を拭い去ってしまったのである。多分大家になってしまった今の彼女は、批評することよりも構築することが自分の使命だと考えているのだろう。けれどもスタイルのない統合は折衷にすぎない。むしろ過去のサープ・スタイルを忠実に再現しようとしたパリ・オペラ座バレエ団の『プッシュ・カムズ・トゥ・ショーブ』が、結局今回の一連のサープ作品の中で最も見応えある作品に仕上がっていたことは偶然ではないであろう。