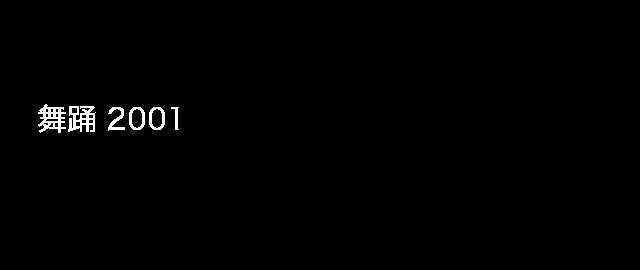二一世紀の舞踊は静かに始まった。二〇〇一年は刮目すべき新人の登場もなく、衝撃的な新作もなかった。しかしこれは舞踊界の低調を示すものではない。当年から新設された朝日舞台芸術賞は演劇のみならず広く舞踊やパフォーマンスをも授賞対象とする。読売演劇大賞が創設されたときおそらく舞踊は眼中になかったのだろうから、舞踊もやっと新聞社の視野に入るまでになったわけだ。審査員の構成は演劇評論家中心であったにもかかわらず、結果は(戯曲のみを対象とする賞と舞踊のみを対象とする賞を除き)受賞九者のうち四者までが舞踊となった。ウェルメイドな作品に票が集まりやすい読売演劇大賞にくらべ朝日舞台芸術賞の方は創造的な試みを評価しようという傾向があるからだろう。それを明確に示すのは、寺山修司賞を設けて舞台芸術の新しい地平を切り開いた個人・団体に与えるとしたことである。その第一回の受賞者は演劇ではなく舞踊の伊藤キムであった。これは新しい舞台形式の探求において、舞踊が演劇よりも活発であることを示しているだろう。じっさい実験的な舞台は演劇よりも舞踊に多い。演劇界では死語となりつつある「前衛」の精神はむしろ舞踊やパフォーマンスの分野に生きている。実験的舞台で知られる解体社などは、初め演劇集団と見られていたが、いまでは「ダンス」のジャンルに入れられることさえある。これは彼らが踊りだしたということではない。「ダンス」の領域が拡大したということである。舞踊家たちの行為によって、ダンスの概念は日々変貌している。今私は片仮名で「ダンス」と書いたけれども、現在の状況は漢字の「舞踊」という言葉では適切でないという感覚がある。「舞踊」という言葉に人々が抱くイメージと現在のダンスとがかけ離れているからだ。これは美術の先端状況を指すのに「現代美術」という言い方より「現代アート」の方が好まれるという事情と似ている。では現在の舞踊家たちは何をしているのか。
まず注意しておかねばならないのは、さきほど前衛の精神が生きていると書いたけれども、なにも六〇年代の前衛の精神が亡霊のように残っているということではない。かつての前衛は、既存の芸術形式の否定と商業主義の否定という二方面作戦を展開する、至って攻撃的なものだった。劣勢で戦う者の常として、選ばれた者であるという自負と自尊だけは大きかった。自尊の根拠は「芸術の本質」は自分の手中にあるという確信である。彼らは絵画の本質、演劇の本質、舞踊の本質を追求し、既存の形式の欠陥を発見しては、それを超克する試みを行ってきた。このとき、彼らにとって絵画とか舞踊とかいうジャンルの存在は自明の前提であった。ジャンルの本質についての反省はやがて「絵画についての絵画」「舞踊についての舞踊」といったメタ芸術を生み出す。これらは研究者にとっては論じやすくていいのだが、観客にとってはたいがい退屈な代物であり、「前衛」衰退の一因となった。しかし現在の日本の先端に立つアーチストや舞踊家は否定への意思を自分のエネルギーにすることはない。既存の芸術形式は依存すべきものではないが、否定すべきものでもなく、ただ利用可能な資源にすぎない。それも、純粋芸術と大衆芸術、近代芸術と伝統芸術などの区別なく、全てが等価なデータベースとして参照されるのである。舞踊でいえば、バレエからヒップホップまでのすべての舞踊だけでなく、スポーツ、武術からサーカスまですべての身体技法が等価な資源となる。身体だけでは舞台はできないから、ライヴの時間と空間とを構成するすべての要素、即ち音響・装置・映像・照明などの技法の蓄積も、しばしば身体と等価な資源となる。振付家の仕事は、一貫した物語を語る作家よりも無関係の断片を組み合わせる編集者の作業に近づく。さらに、少なからぬ振付家は上演現場の空間と観客とを作品のもっとも重要な要素とみなす。いったい彼らは何をしようとしているのか。彼らの作業は「舞踊」の本質の探求ではない。「舞踊の本質」などというものはないし、従って「舞踊の本質とは何か」といった問題設定は無意味だと思っている。なぜなら、ジャンルなどというものは、もともと恣意的な分類にすぎないと知っているからだ。彼らは「本質」という観念から解放されている。では彼らは何に向かって試行錯誤しているのか。未知の経験の発見である。その結果が「舞踊」というジャンルに分類されるか否かはどうでもよい。ただその経験が身体経験であるか、すくなくとも身体を中心としているために「ダンス」と呼ばれることに違和感をもたないというだけだ。だから「ダンス」というジャンル名は明確な定義があるわけではなく、むしろ定義による矮小化を避けるための方略として選ばれたゆるやかな呼称なのである。既知のものに満足せず未知のものを探求すると言う意味で彼らの営為は「前衛」である。そして身体を拠点とする前衛的営為は、たとえダンスらしい所作などまったくなくとも、今日それは「ダンス」と呼ばれてしまうのである。これは観客にとっても同じことが言える。バレエの観客が同時に新劇の観客であることは少ないけれども、コンテンポラリー・ダンスの観客が同時に現代演劇(とりわけ小劇場)の観客であることは多い。彼らは舞踊が好きというより、新しい劇場経験を求めているのである。
未知の経験の探求が作品そのものよりも面白いと思える時、完成された舞台作品だけでなく、その周辺のさまざまなプロセスや、舞踊専門家としての技術を生かしたさまざまな実践が、舞踊家にとって重要な営為となる。他の分野のアーチストとのコラボレーションの増加はその一例である。現代の振付家は、独裁的演出家のように自分のイメージ表現のために他人を利用するのではなく、またカニングハムとジョン・ケージのように互いに無関係に自分の仕事をするのでもなく、むしろ未知の自分を引き出すための挑戦ないし刺激として他者の仕事を利用することが多い。それは時に一種の真剣勝負となる。たとえば建築の伊東豊雄に美術を依頼した山崎広太の振付は、伊東が投げかけた空間への山崎の回答である。もっとも実際には連歌のように、ある程度センスを共有するものが各自の個性を主張しつつ協同と競争を行うことが多い。珍しいキノコ舞踊団とデザインユニット生意気との関係もそうだ。またグループそのものが最初から音楽や映像や美術などの専門家を含んで、舞踊と対等の関係で協同作業をすることも、ダムタイプ以降普通になっている。北村明子のレニ・バッソ、矢内原美邦のニブロール、白井剛の発条トなどがそうである。振付の過程そのものも最近はコラボレーションであることが多い。振付家が予め考えた動きをダンサーたちに与えるというより、課題を与えてダンサー自身に動きを案出させ、そのなかから面白いものを拾い上げ、変形し、構成するのである。振付家の仕事は、頭の中に無から形を創造するというより、ダンサーとの相互の挑発と応戦からシーンを作り、それを集めて一作品に編集することである。海外から舞踊家を招いて、あるいは海外に出て滞在先で作品を作るアーチスト・イン・レジデンスも増えた。たとえばシンガポールのオン・ケンセンは東京で二つの日本のカンパニーと共同で、アメリカのベイツ・ダンス・フェスティバルに赴いた北村明子は現地でコラボレーションする音楽家を探して、作品を作った。これらは作品の完成度よりも、異文化間でのコラボレーションから互いに何か新しいものを発見することに意義がある。CJ8はカナダと日本の八人の振付家(日本側は山崎広太、山田せつ子、島崎徹、伊藤キム)が互いの相手国のダンサーに振付作品を作るという企画だが、これも同様と考えてよい。また舞踊のワークショップが最近盛んだが、初心者がプロに学ぶという初期のあり方を超えて、既に自己の技法を確立したプロへのさらなる刺激の場として機能している。たとえばフィリップ・ドゥクフレが行ったサーカスのワークショップには著名な日本の振付家も参加している(ちなみにこのワークショップの参加者の大部分はダンサーである)。変わったところではNPO法人ASIAS(芸術家と子どもたち)の斡旋による小学校への出張ワークショップがある(木佐貫邦子、日玉浩史、永谷亜紀、伊藤キムら)。学校側は小学生への芸術教育の一環として受け入れているのだが、舞踊家側は子供たちの予想もつかぬ反応や活動を楽しみに授業をしている。これに似た企画としては、モノクローム・サーカスの出前パフォーマンスがある。彼らは交通費と食事だけを対価に私的な場所へ出向いて、必ずしも舞踊愛好者ばかりではない観客に対し歌やゲームを交えつつ即興で場を作っていく。このように、劇場で完成された作品を上演することはなお活動の中心であるけれども、さまざまな空間で異質な他者と出会い、相互に未知の経験を探ることは、今や舞踊家の重要な活動となっている。身体を媒体とした共同作業、遊び、即興、その他さまざまな過程の中で実現される多様な身体営為と経験とは、「舞踊」というより「ダンス」というほうが違和感が少ないだろう。
ダンス公演そのものも劇場や舞台という既成空間の外へ出て行くことが多いし、舞台の上でも一向に踊りらしい踊りのないダンス公演は珍しくない。観客がコンテンポラリー・ダンス公演に求めるものは、やはり身体を媒体とする新しい経験であって、それが「舞踊」の枠に入るかどうかには興味はない。というより、むしろ私たちの「舞踊」についての固定観念を突き崩してくれるようなものを面白がっている。そして日本の若い世代の舞踊家たちは、自分の感覚に誠実であることによって、必ずしも否定への強い意志があるわけでもないのに、軽々と旧世代が自明としてきた約束事を踏み越えてしまうのである。
Flying Cabinet