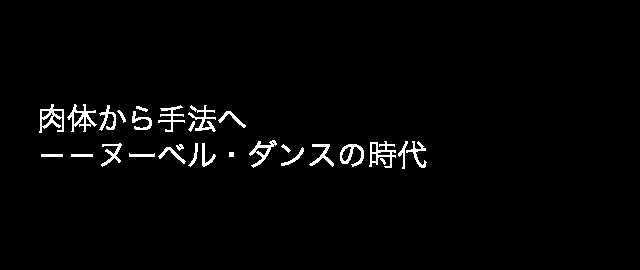「アメリカの時代は終わった」としばしば耳にする。現代舞踊の創造の現場は、ニューヨークからフランスに移ってしまったというのだ。たしかにアメリカのダンスは、ポストモダンダンス以降は刺激的な創造力が涸れてしまったようにみえる。それにひきかえフランスでは、数多くの新しいグループが多様な試みを展開し、新鮮な舞台を次々と送り出している。私としては、ニューヨークという戦場のような街の底力をもう少し信じてみたい気もするが、ダンスばかりでなく美術も演劇もひところの元気がないところをみると、何かが終わってしまったのかもしれない。だが何が終わったのだろう。前衛という神話。モダニズムというイデオロギー。それとも創造の情熱(エイズのせいだという人もいるが)。少なくとも、もはや芸術は戦場で敵を撃破して手に入れるものではなくなったのだろう。ニューヨークでは、創造は既成制度の破壊として行われるものだった。しかしフランスで今行われていることは、決してニューヨークが達成したものの破壊ではない。むしろその継承である。しかもまた、ニューヨークが破壊しようとしたものの継承でもある。 かつて舞踊を見に行くとは、スターを見に行くことだった。いまでもバレエや歌舞伎はそうだ。私たちは『白鳥の湖』や『道成寺』の作者が誰であるかよりも、いったい誰が踊るのかを問題にする。ではスターとは何者か。輝ける身体をもつ者だ。たとえば重力を無視した跳躍を、運動選手の必死の形相ではなく、微笑みながらやってのける者だ。あるいは妖艶な風姿でも、感動的な表現でもよい。その身体に私たちが息をのみ、鼓動を早め、目をみはり、要するにその力に捉えられてしまったことに快感をおぼえるなら、その踊り手はスターである。この意味で、確かにジョルジュ・ドンやバリシニコフ、武原はんや大野一雄はスターである(あるいは、あった)。私たちは、彼らの輝ける身体を見るために切符を買うのだ。
輝ける身体はもちろん容易には得られない。物心つくかつかぬうちに母に手を引かれて稽古場に通い、人並みの遊びをあきらめた長い習練のあげく、何百人に一人の選ばれた者だけが幸運にも手に入れることができるものである。それはほとんど神の恩寵のようなものだ。舞台には時に数十の身体が同時に登場することがある。それでも客席の数百の、あるいは数千の視線は、たった一つの身体に集中する。そして拍手と花束はこの選ばれた者に捧げられるのである。
しかし今日、評価の高い舞踊家はしばしば舞台に見当たらない。その姿をみたければ客席を探さなければならない(たとえばピナ・バウシュならたいがい最後列だ)。彼らは踊り手ではなく、振付家と呼ばれ、カーテンコールにも出たり出なかったりする。しかしたとえ舞台に現れなくとも、拍手はこの振付家に送られるのである。なぜなら、観客は自分の見たものが、振付家の「作品」であると知っているから。「作品」の中でダンサーの身体は、表現の媒体、あるいは組み立ての部品にすぎない。そして「作品」の全体を創造した芸術家こそ、振付家にほかならないのである。 輝ける身体から作品の創造へ。これが近代の舞踊史の一つの特徴である。その過程で舞踊が舞踊であるための条件が問い直され、実験され、限界と可能性が確かめられてきた。その帰結が今日のフランスのヌーヴェル・ダンスであるように思われる。
現在使われるような意味での「芸術」という観念が発生したのは近代のヨーロッパである。この近代的芸術観の中心となった概念は「創造」であった。芸術家は、あたかも神のように、凡人には不可能な創造を行う。詩人は詩を、画家は絵画を、作曲家は楽曲を造る。つまり「芸術家」とは「作品を造る者」である。人々は、それが当たり前だと思っている。ではこれをひっくり返して、作品を造らない者は芸術家ではない、と言ったらどうなるか。役者や演奏家は芸術家ではないということになるだろう。実際役者や演奏家は、人気や収入においてしばしば劇作家や作曲家をしのぎながら、芸術家としての格式において一段低く見られてきた。メニューを読んで周囲を泣かせたという名優の逸話は、観客を感動させるのは戯曲の内容よりも役者の芸だということを証明しているが、近代の芸術観は磨かれた芸よりも作品の創造を重視したのである。西洋の演劇史や音楽史の本を開けば、もっぱら誰がどのような作品を作ってきたかの記述であって、役者や演奏家はほとんど無視されている。ところがバレエ史の本を開けば、記述の中心は踊り手である。バレエとは、何よりも踊り手の身体が観客を魅了するものであり、台本・振付・作曲・美術・演出等はその次の問題であったからだ。たとえば二十世紀初頭パリを驚倒させたロシア・バレエ団伝説の中心にある名前は、ニジンスキーであってフォーキンではない。ではバレエとは特別な芸術だったのだろうか。いや、実はバレエはもともと芸術のうちに勘定されていなかったのである。というのが言い過ぎなら、二流の芸術とみなされていたのである。
十八世紀のノヴェール以来、近代の舞踊家の努力は、舞踊を娯楽から芸術にまで地位を高めることにあった。そのためには、観客に舞踊が「作品」であることを認めさせねばならなかった。これに成功するのは、おそらくバランシンとグラハムの時代になってからである。もちろんそれ以前から作品は作られている。たとえばニジンスキーの振付けた『春の祭典』は素晴らしい作品である(個人的な感想をいえば、ベジャールやグラハムの『春の祭典』をしのぎ、ピナ・バウシュのものにさえ優るとも劣らない)。しかし初演時の不評は有名である。おそらく観客は、ニジンスキーの身体を見にきたのであって、作品なんか見たくはなかったのだ。場所中の国技館で、今日の相撲は中止といって弓取だけを延々と見せたら、どんなに型が独創的でも客は座蒲団を投げるだろう。一方フォーキンの振付けた『薔薇の精』は、作品としては愚にもつかぬものだが、ニジンスキーの超人的な技を実に効果的に見せる仕掛けがあった。人気があったのはこちらである。輝ける身体を期待している観客に作品など出しても受けつけてくれないのだ。その後一九六〇年代までフランスではクラシック・バレエ一本槍だったという。つまり、フランスでは舞踊とはスターの身体を意味したということである。ところがアメリカではバランシンの抽象舞踊とグラハムのモダン・ダンスが舞踊を作品にしてしまったのだ。抽象舞踊とは一種のマスゲームである。一人の身体が突出して輝くのはむしろ邪魔になる。グラハムはダンサーに役者のような嫉妬や憎悪の心理表現を求める。身体は登場人物の内面を表わす媒体であるから、ダンサーの身体そのものが浮き上がっては困るだろう。「作品」の上演のためには、ダンサーの正確なテクニックや表現力は必要であるけれども、もはやスターの身体は必要がない。こうして舞踊は芸術となり、振付家は芸術家となった。生前のグラハムは、アメリカの誇りであった。舞踊作品の創造において彼女が同時代のヨーロッパ人を打ち負かしたからである。
第二次大戦後のアメリカは近代芸術の破壊をはじめた。ニューヨークは世界の芸術の最先端におどりでる。美術ではラウシェンバークが、音楽ではジョン・ケージが、そして舞踊ではマース・カニングハムが登場する(この三人は一緒に仕事をしている、ということは芸術観に似通うものがあったということである)。カニングハムはグラハムを徹底的に否定する。語られるストーリーはなく、表現される感情はない。それどころか、美術や音楽との打合せもなく、起承転結の構成さえない。組み立ての順番はさいころを振ってきめられる。バランシンの抽象舞踊は、たとえ表現内容はないとしても、視覚的効果の計算があり、そのために綿密な構成があった。ところがカニングハムにあるのは、いくつかの動き(ムーブメント)の単位だけである。その組み立ては偶然にすぎない。そしてもちろん輝ける身体もない。カニングハムは舞踊を、何の意味もなく何の表現もない、素朴な身体の動きの最小単位にまで解体してしまった。カニングハムはダンスを、動く身体のほか何の遺産もない出発点にまで返したのである。フランスの現代舞踊はここからはじまる。 一九六〇年代は欧米と日本で既存の文化制度へのゲリラ的反乱が起こった時代であった。とりわけフランスにおいては一九六八年の五月革命が転機となった。舞踊も伝統の圧力から解放され、若いダンサーはかびくさいクラシック・バレエの石室から飛び出した。外には無限の荒野があった。だが彼らはいきなり駆け出したわけではない。どちらへ行けばよいのかわからなかったからだ。そこで彼らは、当時最前衛とされていたアメリカに学ぼうとした。まず影響を受けたのはカニングハムとアルウィン・ニコライであるといわれる。これは興味深い組み合わせである。というのも、現代舞踊史をモダンダンスからポストモダンダンスへという「純粋芸術」の流れとして捉えようとする批評家たちは、カニングハムを神のように崇めながら、ニコライをエンターティンメントに走った傍流とみて無視しがちであるからだ。カニングハムは身体に可能な動きは全てダンスになると考えた。彼は舞台の上であらゆる動きをやってみるのだが、そのとき観客にとってその動きが美しいかどうかには無頓着である。彼に関心があるのは身体の動きの医学的可能性であって、観客にどう見えるかという舞台効果ではない。一方ニコライにとっては観客にどう見えるかが全てである。ダンサーの身体は美術・照明・衣装等と同じ視覚的要素の一つにすぎない。彼の舞台は楽しい視覚的スペクタクルであるが、普通の人が「ダンス」に期待する身体はそこにはない。こうして求道的カニングハムとショー的ニコライとは対照的であるように見える。しかし両者の舞台は、語られるストーリーがなく、感情の表現がなく、スポットを浴びる主役がいないという点で共通していた。つまり、どちらも完全に非クラシック・バレエ的であった(この点でベジャールは中途半端だった)。カニングハムとニコライは非クラシック・バレエの二つの極端を代表していたのである。当時のフランスの若い舞踊家が二人に学ぼうとしたのはこのせいであろう。しかし、アメリカの前衛舞踊が独りよがりの実験を重ねたあげく観客の支持を失っていったのに対し、フランスのヌーヴェル・ダンスが今なおスペクタクル性を忘れないのは、ニコライのせいかもしれない。
カニングハムを乗り越えることでヌーヴェル・ダンスは成立する。そのさいフランスで「グループMA」をつくって活動した故矢野英征の功績は小さくないようである。MAはもちろん「間」であろうが、この時間感覚がヌーヴェル・ダンスにとりいれられた気配はない。影響はおそらく身体の扱い方にある。西欧には心身二元論の伝統が抜きがたくある。この考え方によれば、精神は理性であり霊であって高級なものであり、身体は物質であり肉欲であって低級なものである。かつてバレエが二流の芸術とみられたのも、精神の所産ではなく身体の見せ物であったからだ。グラハムは身体を精神の表現媒体にした。表面に見えるのは身体だが、観客はそれを通して表現された内面に感動するのだというわけである。カニングハムは表現を否定し、身体を内面から切り離した。とういうより内面を切り捨てた。身体という物質さえあれば十分だということである。彼の関心はもっぱら動きそのものにあった。彼の作品からは観念や感情などの意味を示唆する要素は徹底的に排除された。その身体は、動く筋肉以上でも以下でもあってはならなかったのである。これは心身二元論の行き着く先の一つである。
しかし東洋には心身を区別しがたい芸の伝統がある。ヨガや禅を持ち出すまでもない。たとえば能楽師の技量を判断するのにその動きを見る必要はない。ただ構えを見るだけでわかる。だが微動だにしない彼の構えに私たちが感じ取るのは、一体彼の身体なのか内面なのか。たしかに心理や感情の表現はない。しかし彼の身体の相貌は彼の精神のたたずまいを示している。それは脳細胞を含めた全身の細胞がつくり出す人間としての表情である。このとき内面と身体とを区別するのは意味がない。そして動かない構えの緊張感に私たちが息をつめてその身体をみまもるなら、その静止体は既に舞の一部である。「間」とは、そのような音楽となった沈黙、舞踊となった静止を意味する。矢野がフランスで何を教え、フランスの舞踊家が何を学びとったのかはわからない。ただヌーヴェル・ダンスを見て感じられるのは、その動きがカニングハムのような動きのための動きではないこと、むしろ動きそのものより身体そのものに関心があるように見えることである。それも物質としての身体ではなく、人間の身体というものに。即ち、生理的に制約され、文化的に意味を帯び、動くたびにその表情が他人に何かを訴えてしまうような身体である。フランスでの舞踏の評価が(ひょっとしたら日本以上に)高いのも、彼らの舞踊観が「身体の非日常的な動き」から「非日常的な身体の現出」にまで広がっていることを示しているだろう。
さらにおそらくピナ・バウシュの影響がある。彼女の「舞踊劇(タンツテアター)」は、カニングハムたちが排除した、物語や演技や文化的記号や象徴を、つまりあらゆる形の 「意味表現」を復活した。ただし、古典的な舞踊や演劇のやり方ではなく、断片化し、誇張し、引用し、反復し、まき散らし、重ね合わせて。ヌーヴェル・ダンスはこれにならい、あらゆる意味表現の要素をおそれることなく取り入れる。
こうしてヌーヴェル・ダンスは、クラシック・バレエから解放されたあと、何の理念もない場所から(言い換えれば何の偏見も予断もない場所から)白紙で出発し、カニングハム的な「動き」という最小要素からやり直したのである。そして舞踊の要素となりうるものを少しづつ付け加え(言い換えれば復活し)、ついにいまや何でもありという地点にまで来たのである。現在フランスのヌーヴェル・ダンスがもっとも生産的に見えるのは、このあらゆる手法と要素を駆使できる、彼らの自由のためである(もちろん彼らの才能と、彼らを支援するフランス政府の文化政策のためでもあるが)。この彼らの自由は、東西のさまざまな舞踊からただ手法だけを学んでイデオロギーを受入れなかったことにあるようだ。たとえばアメリカの前衛舞踊から動きの最小単位への還元という手法を学んでも、ミニマリズムというイデオロギーは信じない。あるいは矢野から身体への新しいアプローチを学んでも、東洋的身体観は身につけない。全ては作品制作上の手法として学ばれたのである。あとはこれらの手法をどう利用して作品に仕立てるかであるが、ここからは彼らのセンスがものをいう。こうしてエスプリのきいた「ヌーヴェル・ダンス」(新舞踊)が 次々と生まれることになる。
何でもありとは言いながら、彼らはいまのところクラシック・バレエ的な「物語の叙述」や「写実的なマイム」や「優雅な所作」はさすがに敬遠しているようである。だがこれらもいずれ復活するだろう(見方によっては既にしている)。そして今後も、ハイテクからサーカスまであらゆる手法を取り入れ、舞台に組み込んでゆくだろう。多分ただひとつ「輝ける身体」を除いて。
Flying Cabinet