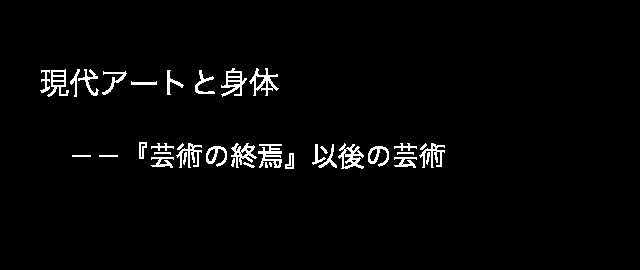「芸術は終った」と言われ始めたのは一九八〇年代だから、もう二〇年になる。『芸術の終焉』とか『芸術の終焉以後』と題する本がアメリカやヨーロッパで次々と出たものだ。けれども廻りを見れば今なお芸術は溢れている。美術展は盛んだし、メディアは芸術の新しいスターを伝えるし、バブル以降沈滞していた美術マーケットさえ元気を取り戻しつつあるらしい。これはどういうことだろう。それらはみんな芸術ではなく、芸術の幽霊だとでもいうのだろうか。それとも芸術の終焉は錯覚だったのだろうか。
いや八〇年代の記憶を想いおこせば、たしかに芸術について何かが終ったという実感があった。だからこそ「芸術の終焉」という言葉がなんの抵抗もなく受け入れられたのだ。では終ったのは何か。まず言われたのは「美術史」の終焉である。「美術史」とは美術現象の全体を「様式の発展」という特定の視点から整理したもので、その背後には美術様式は常に進歩しているという前提があり、その結果として旧様式を否定し新様式を発明する前衛こそが真の芸術だという考えが生まれる。おかげで二〇世紀の芸術史はほとんど前衛芸術の出現史になっていた。しかし一九八〇年頃、新様式の開拓は行き詰まり、折から文化の全領域に流行していたポストモダニズムの影響もあって、美術は古今東西の様式を引用し始めた。様式の発明は放棄され、「前衛」は死語となり、芸術に歴史的発展図式を持ち込む理屈自体がもう有効ではないと言われた。これが「美術史」の終焉である。だがそれだけのことなら何も「芸術の終焉」などと言う必要はない。むしろ芸術は過酷なルールから解放されて、何でもありの時代になったと言えばよいだけの話である。
もっと私たちの実感に近かったのは「芸術という物語」の終焉である。天才とか創造とかいった大げさな言葉と結びつき、芸術家を特権視し、芸術を高尚な精神文化の精華であるとするような、ロマンチックな芸術観の終焉である。こういう「芸術」の観念は一八世紀に西欧で生まれたものにすぎない。この観念は芸術家と職人を区別し、芸術作品と工芸品を区別し、美術館やアカデミー、美術マーケットや文化政策を生み、ついに今日の芸術制度を作り上げた。たとえば以前は礼拝の対象であった聖像が、芸術という制度ができると「芸術作品」とみなされるようになる。すると政府は寺院から取り外して博物館に陳列し、人々はそれを芸術として眺め、その「表現」について感心したりするようになる。しかし八〇年代は世界を説明する「大きい物語」が力を失ったポストモダニズムの時代であった。価値があるものとないものとを区別するいかなる基準も、根元を掘り返すと人為の制度であることが明らかになった。芸術という物語もまたうさんくさいものに見えはじたのである(そしてこれ以降の美術史学や美学は、「美術史」や「芸術」という物語がいかに構築されたかを研究することになる)。シニカルな私たちの眼に、「芸術」の価値を信じて疑わないかのような昔ながらの作品は冷笑の対象でしかなくなった。このあらゆる価値基準を否定するニヒリズム、価値を信ずる者の素朴さを蚩うシニシズムをいったん通り抜けた芸術だけが、見るに堪えるものとなった。そのスタンスはかぎりなくパロディやナンセンスに近づく。つまり既存の世界観の中で意味あるものを作るのではなく、一段高みに立って既存の世界観の奇妙さを拡大して眺めたり、もてあそんだりするのである。このとき作品はいっさいの制度から解放された軽やかさを持つけれども、昔の作品がもっていたような「意味」や「力」を持たない。もし芸術とは意味や力によって人々を感動させるものだとすれば、たしかに芸術は終ったのである。
はじめは面白がっていたポストモダニズム・アートにしだいに飽きてきた私に、再び「意味」と「力」の衝撃をあたえたのがピナ・バウシュだった。彼女は現代のシニシズムもニヒリズムも通り抜けたあと、なお観客を震撼させる芸術を作っていた。生身の身体を使えば、芸術はまだ可能だったのだ。八〇年代後半、私の関心は美術からダンスに移っていった。過去の記憶を辿るために古い原稿を読み返していたら、八八年に私はこんなふうに書いている。「身体はすべてにシラケた人間にとって、最後の意味発生の場所となるのである。そしてこの身体の表現性が、通常経験されるレベルを超えて我々を撃つ時、それを芸術と呼んでも構わないであろう」(『芸術としての身体』勁草書房)。こんな生硬な文章では私が何を言いたいのか読者には伝わらなかったろうが、私は「芸術は終っていない」「芸術は可能だ」と叫んでいたのである。
作家にも美術から身体表現へ転向した者がいる。学生時代に美術を学んでいたフランスのガロッタは、カンバスを捨ててヌーベル・ダンスの旗手となった。ダムタイプの古橋梯二も大学院では絵画を専攻していた。彼は八六年にニューヨークで見たあるゲイのストリップについて書いている。それはエイズを主題とするイベントの最後の演目だった。「その美しい容姿とたくましい肉体はゲイだけではなく女性客をも魅了するものだった。が、彼は全裸になる直前にいきなり自分がHIVに感染していることを公表した。それ以降のストリップで観客は最も残酷な時間を体験した。(中略)我々は呆然と涙を流した。彼に対する憐愍の情からではない。全裸の彼にエロスを感じることすら許されなくなってしまった自分に対して泣いたのだ」(へるめす、九三年五月号)。このエッセイのタイトルは「芸術は可能か?」という。古橋もまた芸術の終焉以降なお「芸術は可能か」と問いつづけ、HIVの身体に涙したとき「芸術は可能だ」と確信したのだ。傑作『S/N』はこの確信がなければ生まれなかっただろう。
これは必ずしもアートの時代が終わってダンスの時代が来たということではない。むしろピナ・バウシュや古橋梯二はアートの系譜に属するとも言えるからだ。たとえば小野洋子はアーチストとして六五年に『カット・ピース』というパフォーマンスを行っている。舞台に座る彼女の衣服を観客たちがはさみで次々と切り取ってゆくもので、その映像が残っている。傷つきやすい肌が露出してゆく彼女の身体に繰り返し刃物が近づく。彼女は明らかにおびえながら、しかし決意をもってそこに身体を置きつづける。これを見る観客が経験する「残酷な時間」の痛みは、八〇年代のピナ・バウシュの舞台を見る時の痛みに近い。たとえば『暗闇の二本の煙草』で上半身を乱暴に剥かれた女性の肌に映画を投射してスクリーンとして使用するのを見るとき。また『S/N』で自らゲイでありエイズであることを告知して裸体になる古橋を見る時の経験も「残酷な時間」だ。これらのシーンはダンスの系譜から生まれたものとは言いにくい。そもそも芸術という制度が終ってしまったあとにアートかダンスかというジャンル分けは意味がないとも言える。ただ「芸術は可能か?」という問いに直面するとき、誠実な芸術家が媒体として身体を選ぶのはきわめて自然なことなのだろう。
Flying Cabinet