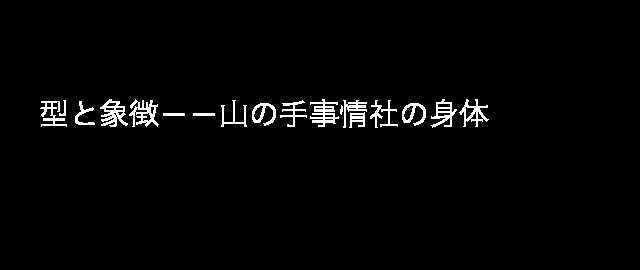今日メガヒットしている映画はたいがい最先端のCGとSFXを駆使したものだ。それらは荒唐無稽な魔法の世界や未来の宇宙をリアルに映像化することに成功し、おかげで観客は虚構世界の物語に没入することができる。これらの映画の興行的成功は当然である。「物語」は昔から人々の求める娯楽であったし、物語を楽しむためにはその物語世界に没入できることが条件だった。しかも没入した世界が日常と遠く離れているほど、物語体験のカタルシスは大きい。だからこそ観客は金を払って物語を買うとき、日常の世界を忘れて完全に虚構の世界に没入できることを求めてきたし、いっぽう物語を売る側も没入を誘うためにできるだけ認知情報をリアルな形で提供しようとしてきたのだ。まもなくテクノロジーは立体映像や体感の変化、さらに触覚や嗅覚の情報まで提供するようになるだろう。観客が虚構世界への没入を求める限り、それは直接脳内の認知系神経を制御するところまで進むかもしれない。
たしかに情報はできるだけリアルであるほうが異世界への没入は容易に起こるだろう。しかし観客自身に没入への用意ができているとき、ほんとうにそこまでする必要はあるのだろうか。たとえば子供が親に「お話」をねだるのは、アマチュアのさして技巧的でもない言葉だけで十分に物語を楽しめることを示しているし、絵本の読み聞かせで興奮したり感動したりするのを見れば、子供はシンプルな挿絵と粗筋だけで物語に没入することができることを示している。いや大人だってマンガで興奮しているではないか。そもそも歴史を振り返れば、物語ははじめ言葉だけで提供されていた。口承の「お話」は日本ではやがて源氏物語などの小説と平曲などの語り芸という形で洗練されていったが、それらに付加された工夫といえばせいぜい絵巻や絵解きという形で挿絵を加えることと、伴奏楽器を付けて音楽化するくらいのことであった。人間の身体が劇的な物語没入を誘う手段として登場するのは事実上中世の能からだといってもよい。しかし中世ではまだ複雑で劇的な物語を提供していたのは語り芸のほうであり、その一つである浄瑠璃が人形という身体を取り込むのはようやく近世初頭である。
ここで問題は、物語の没入には言葉だけで十分であるとしたら、身体はいったい何をすればよいのかということだ。たとえば能の筋書きだけなら、地謡や間狂言がドラマを語って聞かせれば済むけれども、それではシテの身体はいったい何のためにあるのか。むろん語りのほうを捨ててしまえば役者の身体は物語の提示に不可欠になる。じっさい近代の演劇や映画は語りという情報伝達法を捨てた。言葉はふつう台詞だけに限定され、身体の行為と台詞によって物語を説明する。さらに身体は言葉の及ばない表現をしようとする。たとえば性格や心理などの微細な表現である。とりわけ心理についてはドラマの進行に伴ってその瞬間ごとの変化をリアルタイムで表現しようとする。観客はそれを読み取ってドラマの展開に没入するのである。リアリズムという表現理念はドラマがリアルタイムで進行することを前提に、役者の身体をリアルタイムで変化させようというものである。けれども能の身体はリアリズムを目指さなかった。たしかに能では当初から「舞歌」とともに「物まね」を一つの方法としていたけれども、それはリアリズムというより、青年男性の身体でいかに女らしさ、老人らしさなどを表現するかという技術の問題であった。リアリズムが登場人物の個性とたえず変容する心理を表わそうとするものだとすれば、能の物まねは女性一般、老人一般に共通な「~らしさ」という典型性と、身分にふさわしい品位の表現を目指していたのである。しかも能では物語は必ずしもリアルタイムで演じられるものではなく、むしろ語られるものであった。とりわけ夢幻能においては、主たるドラマはすべて過去に終了しており、観客はドラマを目撃するのではなく、そのドラマを回想する身体を見るのである。このときの舞台上の身体は、絵巻物や絵本の挿絵に近い。大人が文字を読むのを聞きながら絵を見つめている子供にとって、絵は一瞬だけ見るものではなく、ある程度の時間を支えるものである。絵はその頁に書かれている文の全てを担っている。ということは、その絵は文章の一部(ドラマの進行のある一瞬)を再現したものではなく、その頁の文全体の象徴として存在しているのである。ここで「象徴」とは、読者(あるいは観客)が言葉から想起した内容の全てを投影することの可能なものを意味する。たとえばその頁の言葉が全体として一人の少女の危機を語っているなら、その絵は少女の危機という事態から読者が呼び起こす感情の全てを受け止めうる(感情移入しうる)図像であることが望ましい。能においても似たようなことが言える。能の時間はリアルタイムには進まない。自由に伸縮し、ときには停止さえしている。身体は写実的に動くとかえって違和感を感じさせるだろう。むしろそのシーン全体の言葉を受け止めることが望ましい。それは動く必要がないことさえある。たとえば居グセは一曲のさわりであるが、ここでは言葉は地謡にまかせシテはまったく動かない。しかしそのシテの身体は連綿と謡われる詩的な言葉をすべて受け止め続けていなければならない。このときシテの身体は象徴となるために、明確な輪郭をもった存在として観客に現前することが必要になる。ただそこにいるだけでは十分ではない。ここに「型」という方法が登場する。それは身体をリアリズムの日常的レベルから象徴の非日常的レベルへと引き上げる方法である。型を得た身体は特定の意味内容を説明する身体ではない。逆に観客が投射するさまざまな思いや解釈を吸収してふたたび観客に投げ返す身体である。つまり観客が(たとえば地謡によって喚起された)自分自身の気分を、あたかも役者の身体の表現として受け取ったかのように錯覚する、鏡のようなものである。言い換えれば、そのとき観客が見たいものを与えるような身体である。ちょうど能面がそうだ。能面はよく表情がないと言われるけれども、特定の表情がないからこそ能面は象徴として機能する。表情とはその都度の瞬間の心理を表現するにすぎないが、象徴となった面は劇的な主人公の運命の全体を引き受けることができる。つい表情を持ってしまいやすい顔を象徴的存在にするには、仮面をつけるのがいちばんよい。それは言ってみれば顔に型を与えることである。型とはCGやSFXとは対極の方法なのである。
むろんただ決められたポーズをとれば型が実現するというものではない。身体が正しく型を身に付けるためには長い修練を必要とする。能の世界では構えるだけ歩くだけでも何年もかかるという。型とはじつは何よりも身体の存在感の問題であるからだ。リアリズムの舞台で見るような日常的身体とは、何かを思い、何かをしようとしている身体である。しかし型は身体に明瞭な輪郭を与えて、一個の建築や記念碑のようにそれ自体で自立させる。日常的身体を前にすると、ひとはまずその内面や行為を解釈しようとするけれども、型を得た身体に対してはまずその存在に目を奪われるのである。逆に言えば、身体は能面に匹敵するほど強い輪郭をもって立ち上がらなければ、観客の濃密な思いを引き受けることはできない。
西洋の影響下に出発した日本の近代演劇がふたたびこのような身体を意識したのは1960年代であった。舞踏の土方巽の近くにいた唐十郎の状況劇場は「特権的肉体」を掲げて異様な身体をテント内に登場させた。しかしその身体はたしかに強くはあったがまだ型という様式性を目指していなかったと思う。鈴木忠志の早稲田小劇場が「劇的なるものをめぐってⅡ」を上演したとき、私が驚嘆した白石加代子の身体には確かに型があったように思う(もう昔の話で記憶があいまいだけれども)。ところが80年代の小劇場は逆に身体から存在感を抹消する方向に向かった。野田秀樹や鴻上尚史の舞台では役者は走り回っていたけれども、運動量に反比例するようにその身体はぺらぺらに見えた。はじめ私はそれを役者の未熟のせいだと思っていたのだけれど、何年たっても薄っぺらな身体にとどまる姿に、どうやらそれは構造的なものらしいと気がついたのである。90年代以降の私は演劇に興味を失い、代わりに舞踊の新しい潮流を追いかけるようになった。そこには身体についての新しい問いかけがさまざまの形で試みられていたからだ。そして21世紀、コンテンポラリー・ダンスがいささか停滞をしているように見える2004年、驚くべきことに身体の型についてあざやかな成果をみせたのは演劇人であった。安田雅弘が主宰する山の手事情社である。
1999年に安田は『印象 タイタス・アンドロニカス』の演出ノートで「私たちが型というものに取り組んで三年になる。日本で舞台芸術を考えるとき、どういうかたちであれ型というものとは明確な距離を取らざるをえない。(中略)私が感じるのは、歴史的に連綿としてあるこの舞台上の肉体(あるいは型)についての感覚はどんなに欧化した文明の中で生きていても、依然として日本人の中には強く脈打っているのではないかということである」と書いている。問題意識は明瞭であった。ただし彼らは能や歌舞伎の型を継承する気はなかった。資産ゼロから現代にふさわしい身体の型を編み出そうとしていたのである。それは試行錯誤の連続になるほかはない。当時の舞台を見た感想を今だから言うけれども、その心意気は壮大だが成功するのは疑わしいと思っていた。山の手事情社が独自に開発した「四畳半」という身体作法は、重心をずらした身体をちまちまと動かすもので、「四畳半」という名が示唆するようにせこい現代日本を反映したものではあったかもしれないが、見ていて面白いものではなかった。なにより役者の身体が弱かった。腰がろくに入っていないのに型をやっても型がきまった感じがしない。様式以前の奇妙なポーズにすぎない。まあ徒手空拳から型を作ろうとすれば、それはしかたのないことだ。一つの身体様式を完成するにはたぶん10年単位の時間がかかるだろうが、それまで果たして役者たちが成否の定かでない作業を続けることができるだろうか、というのが私の疑問だった。ところが山の手事情社はわずか数年でその成果をあげたのである。
2004年に利賀村で上演された『道成寺』は現代演劇にとって重要な作品である。身体が型を持つことによって屹立し、観客の目を奪い、劇的なドラマがその身体によって象徴的に表現されるという、まさに能や文楽において確立された方法が、まぎれもなく現代演劇の形で成功していたからだ。役者の身体はもはやひ弱ではなかった。冒頭、きいたか坊主が並んで座りこんでいるのだが、すでにその存在感は強靱で、彼らが目を動かすだけでほとんど舞踊となっていた。舞台袖から数人がゆっくりと足並みを揃えて登場するとき客席の空気には息詰まる緊張があったし、清姫が波を表わす男たちの身体を踏みつけて川を渡り蛇体となってゆくプロセスは強烈な清姫のパトスを抱えることで劇的な変化[へんげ]の時間となっていた。とりわけ印象深いのは最後に登場した内藤千恵子である。尾のような裾を引きつつゆっくりと舞台中央に歩み出る彼女の姿は、それまで繰り広げられてきた道成寺をめぐる物語の全てを集約するものだった。観客が想起するあらゆる想い、たとえば恋慕・絶望・憎悪・嫉妬・悲哀等々をすべて引き受け、観客が見たいと思うものを鏡のように反射していた。その鮮烈な存在感は、まさに型というものがなぜ舞台に必要なのかを証明するものだった。すなわち、その型を持つ身体は、『道成寺』というドラマの一切を象徴していたのである。
Flying Cabinet