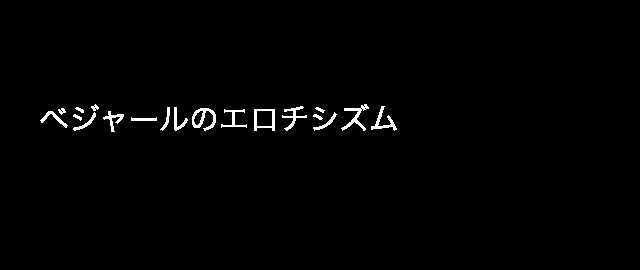ベジャールは自分のバレエ団を「二十世紀バレエ団」と名付けた。この名前はベジャールが自分自身をどのように位置づけていたかを示している。彼はバレエという形式に全幅の信頼を置いていた。二十世紀の思想と芸術の動向に無知であったわけではないが、既存の芸術形式をすべて否定しようとする過激な前衛には与しなかった。しかし十九世紀のロマン主義的なバレエとはまたはっきりと一線を画して、二十世紀の芸術を作ろうとしていた。つまり、二十世紀の思想、美術、文学、音楽などと並べて評価に堪える仕事を志した。では十九世紀と二十世紀の違いは何か。
現代美術の専門画廊に勤めることになった新入りがまず教わるのは、客に商品を勧めるとき決して「美しい」という言葉を使うなということだそうだ。ではどう言えばよいのかというと、この業界では「強い」というのが最高のほめ言葉なのだといわれる。十九世紀、絵画とは美しくあるべきものだった。だが、二十世紀の美術に求められているのは強さである。これは舞踊にも当てはまる。十九世紀のバレエは美しさこそ目指すべきものだった。しかし二十世紀になると、ドイツのマリー・ウィグマンやアメリカのマーサ・グラハムが強い表現力をもったモダン・ダンスをはじめる。ただフランスでは五〇年代になっても十九世紀の美しいバレエが中心だった。そこへベジャールは強いバレエを引っ提げて登場する。それはまさに二十世紀の一撃だった。
ベジャールが自ら「作品1」と呼ぶ『孤独な男のためのシンフォニー』(一九五五)を見てみよう。主題は昔からもっとも好まれたもの、すなわち男女の愛の関係である。十九世紀のバレエはこの主題を美しい音楽に乗せてロマンチックな恋愛観で作り上げる。舞台は異国あるいはおとぎの国であり、恋する男女は理想の身体と心をもつ王子様とお姫様だったり妖精だったりする。愛は純粋であり、永遠であり、その力はしばしば悪魔にも打ち勝つ。衣装はキャラクターを表現するため、あくまでも美しくまた華麗になる。ところが『孤独な男のためのシンフォニー』で鳴り響くのは都市の騒音のようなミュージック・コンクレートである。登場するのは現代の男女である。二人を結びつけるのは無私の愛ではなく、欲望であり、官能である。舞台を支配しているのはロマンチシズムではなくエロチシズムである。みずから主演したベジャールの扮装をみよう。彼は頽廃する社会のなかの孤独な男として登場するのだが、悩める現代青年らしいシャツや背広を着ているわけではない。彼は上半身裸体で現れた。つまりベジャールは衣装によって役柄を表現するという方法を捨て、自身の、生身の肉体をさらけだしたのである。砕け散るようなミュージック・コンクレートの音響のもとで、脈動し汗ばむ肉体が踊る。このなまなましさに比べると十九世紀のバレエがいかに幻想に寄り掛かった虚構にすぎないかが改めて思い知られる。ベジャールのこの作品は、一九五〇年代という時代が要求する、まさにリアルなものであった。そして注目すべきは、バランシンがやはり筋書きを捨て人物のキャラクター表現を捨てていわゆる抽象バレエを推し進めながら、なおダンサーの身体や動きの美しさを追求していたのに対し、ベジャールはまさに強さを追求したことである。
『春の祭典』(一九五九)ではさらに彼の方向が明瞭になる。鹿の交尾に示唆を得たという振付は、もはや人間の男女なのかどうかさえ定かではない。雄と雌の集団の抗争と欲望と交尾と生殖があるだけだ。最近の生物学によれば、生物システムの主役は個々の生体よりも遺伝子であり、それが個々の生体(個人もその一例)を衝き動かして闘争や生殖に走らせるのだという。ベジャールが舞台の上に実現したのは、そのような生体が内部の力に衝き動かされて争い、惹かれあい、抱き合う姿である。もはや個々の生体にキャラクターはない。雄と雌の肉体があるだけだ。ロマンチシズムのかけらもない。しかしその舞台は強烈だった。疾走するストラビンスキーの音楽とともにせめぎ合うダンサーの肉体は、それまで誰も想像できなかった力強さを獲得していた。それは美の理想を追うバレエから見ればグロテスクであるかもしれないが、人間のエロチシズムのもっとも原初的な形が好悪の趣味を超えたなまなましさで立ち上がっていた。観客は「これこそ肉体だ」と思わずにはいられなかった。
そして『ボレロ』(一九六一)が来る。これは人間の男女が古来繰り返してきた関係を純粋に取り出し、増幅したものだといってよい。キャバレーか何かでありそうな光景だが、一人の女の肉体が官能の化身として真っ赤なテーブルの上で踊り始め、取り囲んだ座席の男たちがその肉体を見つめる。欲望に駆られ男たちはやがて一人また一人と立ち上がり、女の動きに自らを合わせて踊り、そしてついに台上の女に襲いかかる。まさに今日のフェミニズムが問題視する「男の視線」(女性を一個の人格としてではなくただ性的対象として見る視線)が舞台空間に劇的な緊張を作っている。男たちの視線を浴びて女が踊るという構図は天の岩戸の前のアメノウズメ以来、ダンスの原型の一つといってもよいくらいありふれたものだが、この構図の背後に在る性と暴力とをこれほど直截に暴露したものはない。しかし不思議なことにこの『ボレロ』は野蛮性や悲劇性を感じさせない。七〇年代以降、フランスのヌーベルダンスをはじめ世界の振付家に性と暴力を主題とすることが流行し、そのほとんどのケースが野蛮と悲劇とを表現しようとしていたのを思い合わせるなら、ベジャールが安易な道を採らなかったことがわかる。ではベジャールは何をしたのか。肉体を輝かせることである。ひとり真紅のテーブルに立つ女は、自分が見られていることを意識している。その肉体は見られるために誇示され、多くの視線を集めることによって輝く。群衆の前の英雄、あるいはファンに囲まれたスターのように、見られる女は見る男たちを支配していると感じざるをえない。だから最後に男たちが、砂鉄が磁石に吸いよせられるように女の包囲の輪を縮めていくときも、女の悲劇というより勝利を感じてしまうのだ。このためにベジャールは女(役名「メロディー」)に見事な振付を与えた。その動きは単純でありながら官能的であり、動物的であり、英雄的である。そしてしだいに激しくなる動きとともに、巫女のように何か超越的なものに結びついているとさえみえる。一方男たちは自分が男であることを確かめるかのようにマッチョな所作を繰り返す。それは見事な肉体をもつダンサーたちによって演じられるとき、まさに男の肉体の輝きを強調するものとなる。それは野蛮というよりも一種の美(ロマンチック・バレエではけっして表現されることのなかった種類の美)であることを認めざるをえない。のちにメロディー役がジョルジュ・ドンによって演じられたとき、『ボレロ』はまた別の姿をあらわした。むろんこれを男の肉体を性的対象として見る、いわゆる「ゲイの視線」の物語と見ることもできる。しかし異性愛者である大多数の観客にとっては、ドンという偉大な肉体の讃歌にほかならなかった。人々は、金髪をたてがみのようになびかせ世界中の視線を一身に呼び集めるかのような、希有の肉体の官能性に酔ったのである。
思えば肉体ほどリアルなものはない。愛だの道徳だのといったテーマは文化や時代が変わればもう通用しない。だが肉体のもつ魅力は人間にとって永遠だろう。たとえ現代社会の建前が「性」を貶めようとも、じつはそのことは変らない。ベジャールはなまなましい肉体を堂々と舞台に立たせ、その官能性を最大限に引き出すことで、かつてない強力なバレエを作りだしたのである。
Flying Cabinet