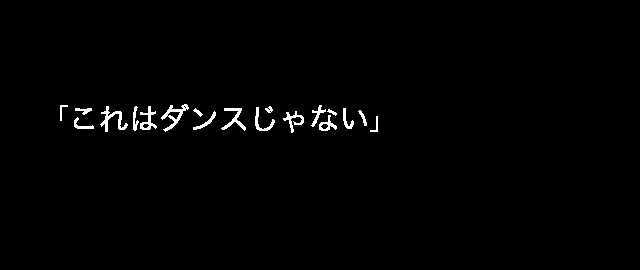気鋭のバレエ団の新作公演を見に行くと、ロビーで「これはもうバレエじゃない」と言う声が聞こえたりする。しかし気鋭の現代舞踊公演を見に行って「これはもうダンスじゃない」という声を聞くのは、ないわけじゃないが、バレエよりはずっと少ないような気がする。それに言われたって、別に悪口にはならない。かつてピナ・バウシュも批評家から「これはダンスじゃない」と言われたことがあったけれども、ピナのファンは「そりゃピナだもの」とか「だからすごいよね」とかいった反応をしていた。これは「バレエ」というラベルにくらべて「ダンス」というラベルが融通無碍であるというだけでなく、どうやら人々が「バレエ」と「ダンス」とでは期待しているものが違うということなのだろう。強引に言ってしまえば、バレエ好きはバレエらしさを期待して劇場に通うのに、ダンス・マニアはむしろダンスらしくないものを見たがっているのだ。
そもそも、とここで話を広げれば、「これはもう~じゃない」というのはバレエにかぎらず他の芸術でも古典的な分野ではよく言われてきた言葉である。どうあるべきかの基準がわりとはっきりしているからだ。肖像画とは本人そっくりに描くものだということになっていれば、ピカソの婦人像はちっとも肖像画らしくないし、有季定型が俳句の条件であるなら無季自由律の句はもう俳句ではないだろう。しかも古典的芸術形式の場合には、その「もう~じゃない」という判定がただちに「だからよくない」という価値判断につながる。ある作品を「もうバレエじゃない」と言う人は、言外に「作品として良くない」とほのめかしているのだ。これに対し現代芸術の歴史は「もう~じゃない」作品の開発競争であったのだが、これは既存の規範に対する二重の挑戦だったわけである。ひとつは肖像画や俳句といった分類のための条件(定義の基準)を否定すること、もうひとつは作品の価値を判断する美意識(価値の基準)を革新すること。世間はどう対応したか。ピカソの価値を認めざるをえなくなったとき、定義の方を変更したのである。「これは肖像画とはいえないけどいいね」とは言わずに「こういう肖像画もありだね」と言うようになったのだ。こういう無節操は芸術家に対する全面敗北のようでそうではない。二重の変更を行うことで「いいものはみんな規範の枠の中」という図式はしっかり守られたのである。たまらないのは芸術家だ。去年の違反は今年の流行、来年の常識ということになれば、「もう~ じゃない」けれども「いい」作品を休みなく自転車操業で開発しなければならないのだから。
事情は舞踊界でも似たようなものだ。一方にクラシック・バレエという古典的分野が あって百年一日の基準で判定され、他方に現代芸術の一部としてのダンスがあってこちらは日々新しい形式と美意識(あるいは価値基準)とを探っている。モダンダンスからポスト・モダンダンスへの展開、ピナ・バウシュや暗黒舞踏の衝撃、ヌーヴェル・ダンスや フォーサイスの実験と、そのときどきの話題にはことかかない。問題は、他の芸術分野でも同じことだが、新しい形式の開発が必ずしも作品の力(価値といってもいい)とは結びつかないことである。今日では、あまりに多くの手法が開発され、実験(規範侵犯の試 み)がやり尽くされて、新人の作家もそれらを取り合わせるだけで一応は新しい舞台ができる。たとえば言葉を喋る、映像を使う、コンピュータを使う、劇場でない空間を選ぶ、観客を参加させる、観客がうんざりするまでじっと動かない、退屈するまで同じことを反復する、等々。だが手法がちょっと風変わりというだけではもう人は驚かない。まして半世紀前の作法で作られる伝統芸能のようなモダンダンス公演(これが案外多い)となると、多少うまい程度のダンサーでは退屈なだけだ。ぼくは客席で寝てしまうことが前より多くなった気がする。
モダンダンス公演にぼくは何を期待しているのだろう。他の現代芸術に対する期待と同じものだ。未知の世界が立ち上がることである。私はその世界に巻き込まれ、呆然としたいのだ。はじめてジェットコースターに乗った子供のように、かつてない感覚に興奮したいのだ。そして持合せの知識も理性も役に立たない錯乱の中で今まで見えなかったものが見えてくるという、あの快感を味わいたいのだ。現代芸術は私たちの感覚と認識の領域を拡張してきた。そして土方巽やピナ・バウシュやフォーサイスはたしかに未知の世界を切り開き、私たちに見せてくれたのだ。そのときの衝撃と興奮の記憶こそ今なおぼくがダンス公演に通う理由である。個人的な経験では、面白い舞台は圧倒的に演劇に多いけれども、強い衝撃を受けた舞台は、数は少ないけれども、ダンスの方にある。まあ少ないのは仕方がない。どんな分野でも独創的な仕事ができる作家はほんの僅かだ。それに優れた作家でも作品に出来不出来はある。バレエ公演の場合は予想した水準から大きく外れることはないから「金を返せ」と思うことは滅多にないけれども、現代舞踊はつまらないからといっていちいち腹を立てていたら血圧がもたない。ダンスの切符は馬券のようなもので、たいていは外れるけれどもたまに当たれば配当は大きいのだからと割り切るほかはない。
さて土方やピナ・バウシュは「もうダンスじゃない」と言いたくなる舞台をつくりながら、作品の力によって「こういうダンスもあり」と認めさせてダンスの領域を広げてきたわけだが、この領土拡張はどこまでいくのだろう。ロバート・ウィルソンはさまざまなイメージと音楽とダンスとが交錯する自作を「オペラ」と呼んだけれども、ある学者は既存のジャンルに分類できないという理由で「パフォーマンス」と呼んだ。六十年代以降「もう音楽でも演劇でもダンスでもない」という実験的作品が次々と出現したが、そういう舞台はとりあえず「パフォーマンス」というラベルで処理しておこうという苦肉の策だった。この場合「パフォーマンス」はいちおうジャンル名であるけれども、積極的な定義があるわけではなく、どのジャンルの定義にもあてはまらないものというゴミ箱のような概念 だったから、一時は便利に使われたけれども結局定着しなかった。いまでもたいていのメディアは「パフォーマンス」などという分類は使わず、新しい様式の舞台作品は「音楽」か「演劇」か「ダンス」のどれかにむりやり入れてしまう(英語には「パフォーミング・アーツ」という便利な言葉があるが、これは「ダンス」の上位概念で、観客の面前で身体が何かをしていれば「音楽」も「演劇」も「ダンス」も、そのどれともつかないものもみんな入ってしまう)。そして興味深いことに、今や分類に困ったものは「演劇」よりも 「ダンス」に放り込むことが多いようなのだ。これが六〇年代だったら、いや七〇年代でも、わけのわからないものは多分「演劇」に分類しただろう(ロバート・ウィルソンの作品は「イメージの演劇」と呼ばれたこともある)。なぜ今は「ダンス」の方が度量の広いラベルになってしまったのだろう。おそらくダンスの作家の方が従来の境界線を破ろうとすることに果敢であるからだ。その理由は、演劇人が「演劇とは何か」「演劇が成立するための必要条件とは何か」と考えることよりも、舞踊家が「ダンスとは何か」「ダンスの成立条件とは何か」と考えることの方が多いからだ。逆に言えば、ダンスの方が危機は大きかったのだ。演劇は根源的な反省などしなくとも、脚本や演出の工夫で新しい様式ができる。しかしダンスは身体について、上演ということについて、根本から考え直さなければ新しいものを作ることができない。演劇には脚本というものがあるため、作家は脚本のレベルで実験がいくらでもできる。たとえば物語を解体して奇妙な形で再構築したり、虚構の登場人物と現実の役者との二重性を利用したりと、簡単にメタレベルの操作ができる。さらに言葉はいくらでも現実を無視することができるから、これを駆使すれば観客の意表をつく実験は造作もない。しかしダンスはもともと言葉を持たないうえ、現代のダンスは台本を、つまりバレエが持っていた物語や登場人物を捨ててしまったため、身体そのものについて、あるいは上演形態そのものについて考え直してみるほかないのだ。それはたとえば、着衣の民族が毎年新しいファッションを生み出すのは簡単だけれども、裸族が今年は新しいイメージで出てこいと言われたら、身体そのものについて、あるいは歩く坐るといった基本的な動作について考え直すことを迫られるのと似ているだろう。こういう注文はたいていの人には無理難題でしかないけれども、本当に才能のある作家にとってはむしろ常識の壁を打ち壊すきっかけとなる。ダンスの危機の深さは却って「ダンス」の領域の拡張に(あるいは旧来の「ダンス」という概念の無効化に)力を貸したのである。
探究のひとつの方向は自身の身体を拠り所にするものである。これは振付家が同時にダンサーである場合に多い。舞踏家はもちろん、日本人の舞踊家はしばしばそうだ。かつて土方は毎晩自分のからだの中へ梯子を下ろして降りてゆくと言ったけれども、これは今なお多くの舞踏家たちの実践でもあるだろう。あるいはかつての田中泯のようにさまざまな(舞台以外の)場所で踊り、その環境と身体との接触を繊細に意識し、身体が場所に触発されて変容したり、逆に場所が身体によって相貌を変えるのを手法とすることもある(彼はこれを「場所の殻を剥がす」と表現した)。今や日本を代表する振付家となった勅使川原三郎も身体と環境(空気とか)との交感を強調する。
もうひとつの方向は作品構築のやり方を素材と構成の両面で革新してゆくことである。これは自分で踊ることをやめて振付に専念するタイプの振付家に多い。また西欧の振付家はたいていこれである。最近の流行は素材を自分で考えずにダンサー自身に委ねるものである。現在世界最高の振付家といえばピナ・バウシュとウイリアム・フォーサイスが人気を二分するだろうが、二人とももはや動きの細部を自分で作ることはしない。ピナ・バウシュはダンサーたちにさまざまな問いかけをして返ってきた言葉や動きを素材に作品を組み立てる。フォーサイスは動きの変化のルールを予め作っておくが、実際に舞台でどう動くかはダンサーの即興にまかせる。この二人に継ぐ位置にいるケースマイケルは、稽古場でダンサーたちに即興の動きをやらせ、それをもとにさまざまな変形を加え、切ったり継いだりして一連の動きを作成する。彼らのやっていることは、自分が考えた動きをダン サーに教える古典的振付法ではない。「これはもう振付ではない」と言ってもいいくらいだ。構成・演出と言ってもいいが、編集というのが一番近いだろう。いうまでもなくこれらの舞台では、ダンサーの身体は作品の一要素にすぎず(一番重要ではあるとしても)、空間・言語・音楽(というより音)・照明・美術(というか装置)・映像などあらゆるものが利用されるのが普通である。かつて舞踊を他ジャンルと差別化するために排除された台詞や、キャラクターのはっきりした衣装なども今は平気で使われる。それによりかかることさえしなければ、編集の素材は何でもありなのだ。それどころかダンサー商品化の象徴としてあれほど毛嫌いされた官能的「女の美」を臆面もなく舞台に乗せる荻山幸子のような者さえいる(もちろん彼女はその「雌の理想像」をアイロニーをもって編集するのだけれども)。
だがさらに注目すべきは、ダンスを、舞台という狭い空間と上演という短い時間のなかだけで完結する一時的幻影にとどめず、もっと広いコンテクストの中に置こうとする試みであろう。たとえばビル・T・ジョーンズの作品『スティール・ヒア』(まだ・ここに)は舞台の上だけを見るかぎりではさして面白いものではない。しかし彼がアメリカに住む黒人であり、ホモセクシャルであり、エイズの感染者であることを知るとき作品の意味は変わってくる。「まだ・ここに」という題名は、まさに彼自身の身体が「まだここに生きている」という眼前の事態を指している。さらにこの作品の素材が、不治の病に侵された多くの患者の協力によってできていることを知るとき、目の前のダンスの背後に「まだこの世界に辛うじてとどまっている」無数の人々の生が見えてくるだろう。観客に求められているのはダンスそのものを鑑賞することよりも、それを成立させているコンテクストを見つめることである。ちょうどアラーキーの私写真が、一枚の画像で自己完結するものではなく、その写真を成立させているコンテクスト、つまり荒木自身の私生活をその背後に立ち上がらせるように。同じことがダムタイプの傑作『S/N』にも言える。泥臭いコントと洗練されたコンピュータ映像、疾走するダンスとドラァグ・クイーンの口パク唱歌、執拗な政治的メッセージと本物の娼婦のうちあけ話などのごった煮のようなこの作品は、作者であり主演者であった古橋梯二が実際にホモセクシャルであり、エイズの感染者であることを観客が知っていたからこそ大きな感動を与えたのだ。観客は上演された全ての言葉や行動から彼の実人生が置かれているコンテクストの歪みを実感し、そのコンテクストがまさにぼくたち自身の生きている社会にほかならないということに動揺したのだ。「場所の殻を剥がす」田中泯の作業もこれに近いだろう。それはダンスのコンテクストである場所の相貌を変えるのである。
客席と断絶した舞台とは、その上で行われている全ての言動を「これはみんな嘘だから安心して見てね」と観客に教える仕掛けである。しかし上演のコンテクストが現実の世界に広がってゆけば、作品のあり方には未知の可能性がいくらもあるだろう。ダンスの領域はどこまでも広がっていくだろう。先日テレビで無名の若いデザイナーのファッション ショーのドキュメンタリーが放送された。そのショーは周到に設営された空間に客を招き入れるものではなく(たぶん会場を借りる金が不足していた)、奇抜な衣装と髪型とアクセサリーを身につけた数人のモデルが歩行者天国の原宿を闊歩するというものだった。その異様ないでたちと颯爽としたモデル歩きはどう見ても普通の歩行者ではなく、通りがかりの人々を立ち止まらせて、十分にパフォーマンスとして成功していた。しかし写真や握手を求める者がいると彼女たちはたちまち友人のように楽しげに交流し、祭りの中に溶け込むのだった。むろんこの空間を祭りに変えたのは彼女たちの存在である。しかしたまたま通り合わせた人にとってこの祭りはお芝居の虚構ではなく、彼らも参加できる街の現実だった。触れる物を全て黄金に変えた王様のように、歩む空間をたちまち祝祭に変えてゆく眩いばかりの彼女たちの振舞を見ながら、ぼくは「これはもうダンスだ」と思っていた。
Flying Cabinet