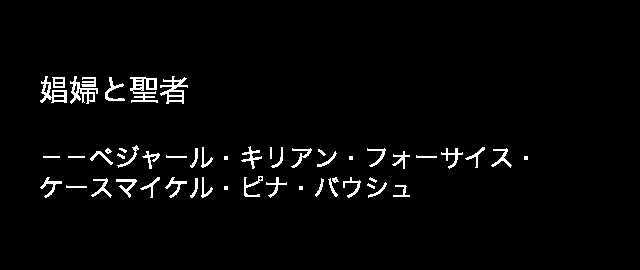「芸術家は、まさに娼婦なのだ!」
これは江戸初期の遊女歌舞伎のことではない。ベジャール自伝中の言葉である。趣意は、作品は芸術家の自己満足のためにあるのではなく、観客に一夜の快楽を提供するためにあるということだ。この「観客のための芸術」発言はおそらく「芸術のための芸術」という近代的芸術観を念頭に置いている。ベジャールが活動を始めた一九五〇年代、アメリカではマース・カニングハムが純粋な舞踊の可能性を探究していた。それはまさに「舞踊のための舞踊」であった。この同時代のもう一人のヒーローをベジャールが意識していなかったとは思えない。とすれば、彼の右の台詞は、自分がアメリカ的モダニズムの求道者ではなく、むしろ観客に提供する快楽の質を最上のオペラや演劇に劣らぬほどに向上させて、舞踊が芸術であることを有無を言わせず納得させた、プティパやディアギレフのロシア・バレエの後継者であることの宣言であったともとれる。カニングハムが舞踊道の聖者であるとすれば、ベジャールは娼婦であることを選んだのである。
もっともアメリカと違い、一九五〇年のフランスではまだ「舞踊のための舞踊」は認知されていなかった。舞踊とは即ちクラシック・バレエのことだった。それは児童劇のような単純な筋書と役柄、サーカスのような身体の曲芸、そして遊女歌舞伎のようなスターの魅力から成る。ベジャールの新しい「観客のための舞踊」はこれらと訣別することから出発した。
彼が自分の最初の作品と呼ぶ『孤独な男のためのシンフォニー』はお姫様と王子様ではなく、現代の男と女の関係を取り上げる。衣装は役柄を語らず、ダンサーを飾ることもしない。男は半裸でズボンを穿き、女はタイツだけである。叙情的音楽に代わって荒々しいミユージック・コンクレートが耳を叩く。所作は、流れるような優美ではなく、鋭く突発しあるいは官能的にゆらめく。それはまさに「前衛」的手法であった。しかし手法という表皮を剥がせば、この作品の核にあるのは、男と女の愛憎というテーマと、身体の動きがもつ表現力の拡張である。それまでのバレエが目指していた身体表現は、役柄(たとえば清純な王女)であり、感情(たとえば悲しみ)であった。これに対しベジャールが提示したのは、猫の身体がもつ官能性やライオンの身体がもつ凶暴性を人間の身体もまた持ちうるということであった。明確なテーマと身体の魅力。これを、ほぼ同時期にカニングハムが行っていた実験、即ち舞台から一切の意味を剥奪し、運動の抽象的構成に還元する舞踊と比べてみれば、その違いは明らかだろう。カニングハムの自律的舞踊には観客への効果という視点がない。ベジャールは観客に何かを伝え、力を及ぼすことを目指している。カニングハムが求道の聖者なら、ベジャールは誘惑する娼婦である。その後のベジャールの歩みは、よき娼婦であろうとした軌跡と見ることができる。舞台は華麗な大スペクタクルとなり、死や愛といった大文字のテーマがさしたる深さもひねりもなく押し出される。彼の振付と演出の力量は認めながらも、この大時代な素朴さに鼻白む人は多い。けれども彼の振付の重要性は、演劇的表現力にではなく、ダンサーの身体の魅力を引き出してきたことにあるだろう。その典型は『ボレロ』に見られる。主役のダンサーに求められるのは役柄や感情の表現技術ではない。ただ身体そのものの魅力である。だからダンサーが代われば全く違った作品になる。そしてどれほど技術を持つダンサーでも身体が魅力を発散できなければ、作品は無残になる。他のベジャールの作品でも男性舞踊手はしばしば上半身を裸に剥かれ、動作は生臭いまでに肉体を強調することが多い。貧弱な身体は耐えられないだろう。たしかにどんな舞踊もダンサーの個人的力量に左右されるけれども、ベジャールの振付は特にその依存度が大きい。そして要求されているものが単なる技術や容姿ではなく、個人的な身体の力であるという点で、しばしば残酷である。しかもこの力はソリストだけでなく、コール・ド・バレエにまで要求される。だが、だからこそ彼の作品が成功するとき、観客は十分な快楽を味わうことができるのだ。一流の娼婦と出会った夜のように。
娼婦ベジャールの後継者はイリ・キリアンである。彼はベジャールの欠点と思われたものを取り除いた。知識人が嫌う浅薄なテーマ性と、保守派の嫌う肉体の生臭さである。おかげで彼の作品は強い衝撃を与えることはないが、誰からも嫌われることがない。彼の属するネザーランド・ダンス・シアターは、もともとバレエに抗して五十年代末に設立されたもので、舞踊界の反体制派を自認していたのだが、いまではオランダ女王が外国元首の接待に使うまでになってしまった。国歌の響く劇場で、いつのまにか体制派になってし まったことにキリアンは戸惑いながら、しかし認められるのはいいことじゃないかと語る。そう、キリアンは最初から認められてきた。ベジャールの『春の祭典』の初演は観客から口笛攻撃されたが、キリアンはいつも気に入られた。彼の考える革新とは、バレエの拡張であって、否定ではない。観客は期待したものを手に入れるが、予期せぬ視点や感性に驚かされることはない。たとえばニジンスカ振付の『結婚』は通常のクラシック・バレエとは全く異なる美意識で作られ、観客は異世界を覗いているような気分になる。ところがキリアンの『結婚』は、ニジンスカの振付からいくつかの型を取り入れるが、それらは気のきいた思いつき程度にしか見えない。観客の感性は挑発を受けない。ただキリアンの豊かな思いつきと巧みな構成とを楽しむのである。実際彼の作品は才気に溢れている。凡庸な振付家が一年に一つ思いつけるような所作を、キリアンなら一時間に五十は思いつくだろう。たいしたものだ。だが逆に言えば、彼のアイデアの一つ一つは凡庸な振付家でも思いつける程度のものである。彼は新しい地平を拓く革命家ではない。けれども、もし世界の振付家たちがブロードウェイで競争したら、一番人気はキリアンだろう。売れっ子になるのは、結局誰からも好かれる娼婦なのだから。
聖者カニングハムの跡を継ぐのはフォーサイスとケースマイケルである。もっとも二人のやり方はまるで違う。フォーサイスの手法は『セイム・オールド・ストーリー』によく表れている。長いテーブルの両端に男女が座っている。男は遠くの女に話を始める。「むかしむかし・・・」。誰もが知っているお伽話だ。その横でこれと無関係に十数人のダンサーが幾何学的な群舞を始める。観客はダンスを背景にしてお話に耳を傾ける。だが耳新しい話ではない。それよりも鋭くダイナミックなダンスの方が面白い。そこでお話を背景にダンスに注意を集中する。ふと気がつくとお話が妙な具合に進んでいる。百年間眠ったお姫様は継母と二人の姉に苛められ、森の中で七人の小人に会う。幾つかの話がごちゃ混ぜになっているのだ。それに男と女の距離もいつの間にか縮まっている。ダンサーたちは相変わらず無関心に、コンピュータで構成したと言われる複雑な振付を猛烈なスピードで展開していく。最後に男は「そして王子さまはお姫さまにキスをしました」と言いながら、女に接吻して舞台は終わる。フォーサイスの書いた台本は物語を拒否しているわけではない。ただ複数の物語を解体し再構成しているだけだ。逸脱と辻褄あわせとが目まぐるしく交替し、最後にキス一つですべてのお話はみごとに完結する。クラシック・バレエやマーサ・グラハムのモダンダンスが明確な物語を持ち、カニングハムがこれに対して一切の物語を拒否したことを思えば、物語を解体し奇妙な形で再構築する彼のやり方はポストモダン的とも言えるだろう。同じことは振付にも当てはまる。クラシック・バレエではソリストという焦点とコール・ド・バレエという背景とははっきりと分かれている。カニングハムはこれを否定して一切の空間を均質化し、焦点と背景との区別をなくした。しかし観客の眼は全体を均一に見ることなどできはしない。たいていどこかに焦点をあてて見るのである。地の中に図を見出そうとするのは人間の生理かもしれない。そこでフォーサイスは地と図を復活する。ただし、この地と図は目まぐるしく交替するのである。もはや図は地に対して価値の優位を持てない。地と図の関係は意味発生の仕掛けとして意義を失うのである。舞踊や物語をメタレベルから分解し再構成する手付きを観客に提示する彼の舞台は、現在最もスリリングなものであろう。
一方ケースマイケルはもっと素朴に身体と運動とにこだわる。わずかなズレを含みながら単純な動作を反復する振付は、カニングハム以後アメリカに現れたミニマル・ダンスに似ている。違うのは、ミニマル・ダンスが身体性を消して純粋な運動を提示しようとしたのに対し、ケースマイケルの方は身体の表現性を意識的に操作したことである。ただしそれはベジャールのような身体そのものの力ではない。ある種の所作が持っている文化的意味作用である。もっとはっきり言えば、ジェンダーとしての「女」に属しているさまざまの記号的身振りである(これはベジャールが主として男のために振り付け、ケースマイケルの舞踊団ローザスが女性ばかりのグループであることとも関係しているかもしれない)。だからベジャールと違ってダンサーは身体的魅力を要求されない。記号的所作を正確に演技できる技術さえあればよい。ケースマイケルはカニングハム同様、ダンスとは身体の操作だという視点から、その基本条件を探ろうとする。単純な動きの力強さ、僅かなズレのもたらす複雑さ、最小限度の記号的所作がもつ明確な表現力。これらの組み合わせは、意外なほどに強力なダンスとなった。彼女はカニングハムの捨てた身体の表現力を再び拾い上げたとはいえ、舞踊を基本条件に還元してゆくその精神はカニングハムを引き継いでいるといえるだろう。
「観客のための舞踊」と「舞踊のための舞踊」という二つの立場の外にいるのがピナ・バウシュである。彼女のやっていることはただ「自分自身のための舞踊」であるように見える。ピナは娼婦でもなく聖者でもなく、いわば私小説作家なのだ。彼女は自分が何者であるかを確かめるために舞踊を作る。いや舞踊と呼ぶのさえもはやためらわれる。彼女の作品では、いかにも舞踊らしい動きは少なく、むしろ日常的行為や所作の断片が様式化され、組み合わされて提示される。統一された物語はなく、人生の破片が散らばっているだけだ。あるものは美しく、あるものは残酷に。だがそれら無数の破片は、すべてピナ・バウシュという一人の人間の眼差しを映し出している。観客がこの眼差しを共有するとき、人生とは統一的な物語ではなく断片の集積であること、そしてそれらはとても美しく同時にとても残酷であることを理解するだろう。彼女の扱う素材に名札を貼って分類するなら、ベジャール同様「愛」とか「死」とかいうことになろう。しかしベジャールの「愛」が抽象的な観念であるのに対し、ピナのは具体的な男と女ののっぴきならぬ関係である。ベ ジャールの「死」が崇高な理念であるのに対し、ピナのは暴力への恐怖であり、あるいは忘れえぬ者への追慕である。しかもその眼差しは二重三重に屈折しており、たとえば共感と皮肉と諦観とが一つになっていたりする。観客はただ自分を開いて全てを受入れれば、ピナ自身の不安と恐怖、愛と希望を一つに溶け合ったものとして共有できるだろう。観客はベジャールの言い分を頭で理解できるが、ピナの告白は身体で理解するしかない。だが身体を媒体とする芸術を舞踊と呼ぶなら、ピナは確かに新たな舞踊の地平を拓いたのであり、「舞踊のための舞踊」を目指す求道者たちに大きな示唆を与えるだろう。また観客に感動を与えることが舞踊の目的だと考えるなら、現在ピナの仕事は最大の成功を収めているだろう。能『江口』の主人公のように、彼女は娼婦にして聖者なのかもしれない。
Flying Cabinet