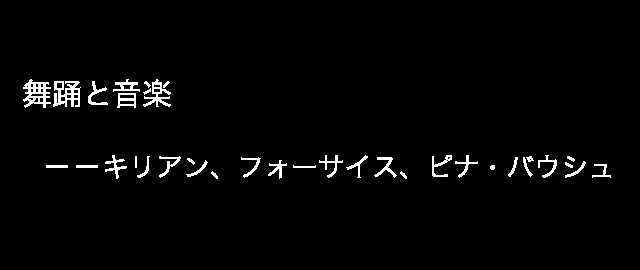二月、フォーサイス。四月、ピナ・バウシュ。そして六月にはイリ・キリアン。今春は世界の舞踊界を先導する大物が相次いで来日した。三役揃い踏みである。
キリアンの『輝夜姫』は彼の作品の中では出色であろうが、その成功は作曲者石井真木の構想に負うところが大きい。石井はこれを打楽器と雅楽楽器だけで構成し、天上の人たる輝夜姫には雅楽を、地上の支配階級には西洋型打楽器群を、農民には日本太鼓群を割り当てた。この着想は面白い。というのも、この楽器群の違いは、実は音楽を支えるリズム感覚の違いを伴い、従ってそれぞれのダンサーは全く性質の異なる舞踊を要求されるからである。西洋音楽は一般に明確な構造の反復であり、抽象的な数字でカウント可能なリズムをもつ。だが和太鼓の演奏は呼吸と間が鍵であり、機械的にカウントするとリズムは死んでしまう(日本舞踊家は鼓が「こけ間」になると踊れないという)。そして雅楽のリズムは石井に言わせれば「悠久の時間」であり、どこが頭やら尻尾やら捉えようもない。キリアンはこの三者の対比を衣装や配置など演出の工夫によって強調し、振付においても (和太鼓の特徴はあまり生かされなかったが)打楽器の前進的時間と雅楽の停滞的時間との違いをわかりやすく提示していた。彼は石井の意図を正確に読み取り、見事に視覚化したのである。この公演を見た舞踊家の知人は、「キリアンの音楽の解釈力は素晴らしい」と絶賛した。私は、まあそれはそうかもしれないけど、と肯定しつつ何かしら釈然としない気持ちが残った。多分、舞踊家が音楽を解釈してどうなるのだ、という思いが心のどこかにあったのだ。
舞踊は身体の芸術だと言われる。当たり前のような話だが、では純粋な舞踊を目指して身体以外の要素を排除したらどうなるか。実際今世紀の舞踊は物語を排除し、表現を排除し、美術を排除しといった具合に実験を試み、成功してきた。だが、音楽だけはなしで済まそうとするとどうもうまくゆかないのだ。もちろんダンサーは音楽なしでも踊れる。練習では「一・二・三」のカウントだけで動くことも多い。だからやってできないことはないが、端的に舞台がつまらないのだ。たとえ音楽というより雑音に近いものであるとしても、何かの音のデザインなしに舞踊が試みられることは、今やほとんどない。
音楽なしで済まないとすれば音楽とどうつきあうか、というのが現代の舞踊家の課題である。古典的なやり方は、まず筋書をもとに台本を作り、これに基づいて作曲と振付を行う。音楽と舞踊は協同して内容を説明するわけである。クラシック・バレエのほとんど全て、モダンダンスの大作の多くはこれだ。これと対極にあるのがマース・カニングハムとジョン・ケージのやり方である。カニングハムの振付とケージの作曲は、没交渉のまま 別々に進められ、公演当日の舞台で初めて互いの仕事を知る。二人の共同作品は、音楽と舞踊とが「無関係」であるように仕組まれている。ダンサーは音楽に耳を傾けない。ただ頭の中でカウントを数える。観客は舞踊と音楽を同時に知覚しながら、そこに「偶然」の関係、あるいは「無関係」の共存を見出す。ちょうど自然の中の風景と音とが偶然に出会い、無関係に共存しているように。
右の前者を「協同型」、後者を「偶然型」とすれば、この中間にさまざまなタイプがある。比較的前者に近いものに「解釈型」があり、後者に近いものに「対決型」がある。解釈型とは、既存の音楽に新たな解釈で振付を行うものである。たとえばストラビンスキーの『春の祭典』に、私たちはニジンスキーのみならずグラハムの解釈、ベジャールの解釈、ピナ・バウシュの解釈を見ることができる。このタイプが現在最も一般的だろう。新曲を委嘱する資金のない、あるいは信頼して協同作業を進められる作曲家のいない場合もあるが、既存の音楽を漁って自分の創作意欲を刺激するものを発見するというやり方の振付家が多いからである。一方「対決型」は、既存の音楽を使うにしても、その音楽に合わせて振付けるのではなく、音楽の目指すものとは別に自分の世界を舞踊によって作り上げるものである。その代表は、咆哮するトム・ヴィレムスの音楽を猛獣使いのように調教し、ダンスのBGMにまで飼い慣らしたフォーサイスであろう。もっともこのタイプの一方の端は解釈型と区別がしにくい。たとえばベジャールの『ボレロ』は、楽曲の新しい解釈であると同時に、楽曲を超える世界を舞踊が提示したという意味で対決的でもある。またこのタイプの他方の端は偶然型と区別しにくい。前衛音楽や雑音を使う前衛舞踊の場合、しばしば音楽と舞踊とが密接な関係を持たないようにと配慮されている。振付家が選択した音楽であるにも関わらず、舞台上の舞踊と音楽とはあたかも偶然に出会ったかのように振る舞うのである。日本の舞踏系の公演にはこの種の演出が多い。
この対決型の一変種として「引用型」とでもいうべきものがある。ピナ・バウシュは古今東西の音楽を自在に引用しコラージュする。日本の歌謡曲さえ利用される。だがそれらは必ずしも本来のイメージのまま使われはしない。しばしば壮大な音楽は誇大妄想的に、ノスタルジックな感傷歌は滑稽に、能天気な流行歌は悲劇的に響く。それは楽曲が潜在的にもっていた特性を新解釈で引き出したということではない。ピナの舞台では人間の表層が剥がされ、いたましい人生が顕れる。そこでは音楽は、壮大であるがゆえに誇大妄想的に、感傷的であるがゆえに滑稽に、能天気であるがゆえに悲劇的に聞こえるのである。今春来日したピナ・バウシュはインタビューに答えて、自分にとって音楽はとても大切なものだと言い、しかしカニングハムやフォーサイスのような作曲家との協同作業はするつもりがないとも言った。彼女は世界中の既存の音楽を漁る。しかし彼女はその音楽の表現内容に共感してはいない。そのような音楽のもつ制度的意味と個人的意味と生理的効果の落差に注目している。たとえば他人の誕生日を祝う歌が自分には孤独を確認する歌であったりする。ピナは音楽に合わせて何かを表現するのではない。逆説的な生のドラマを伝えるために音楽を逆説的に引用するのである。そんな彼女が作曲家と協同できるはずがない。
今日注目すべき舞踊家は、たいてい広い意味での対決型に属している。解釈型の作品は、熟練の振付家なら容易に高い完成度を持つけれども、舞踊が音楽の内容をなぞるだけでそれを超えることがないためか、どこか物足りないのだ。ただ音楽自体が従来の枠組を越えようとしているとき、解釈型の振付も新鮮な成果を得ることができる。あれほど多くの舞踊家が『春の祭典』に魅せられたのも、キリアンが『輝夜姫』を選んだのも、それを知っていたからだろう。
Flying Cabinet