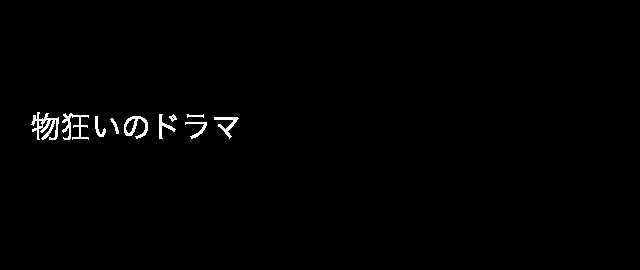小学生で落語に、中学生で歌舞伎にはまった私だが、高校生になって初めて能を見たときは退屈のあまり寝てしまった。禅竹弥五郎の狂言『月見座頭』には私の芸術観をひっくり返されるほどの衝撃を受けたものの、能については現代に生き残る理由がないように思えた。その後世界の前衛演劇の数々の実験を見て、ようやく能が舞台芸術として現代でも卓越した形式であることを知ったのは十年以上後のことである。それでも、人間のドラマとして見るときは、近代劇はもちろん西欧の古典劇あるいは近松らの浄瑠璃に比べても素朴すぎるように思っていた。 その考えを改めたのは友枝昭世を見てからである。
友枝昭世の舞台では、事前に台本から予想していたのとはまったく違うドラマが現れる。たとえば『松風』は男に捨てられた二人の女の話である。一人は現実を冷静に見ている。もう一人は現実を受け入れることができず、妄想の果てに狂気に陥る。これは恋に狂った女の哀れさを見せる演劇だ、と私は思っていた。それが常識的な解釈だろう。ところが舞台を見ると、狂った女こそが幸福であり、狂うことのできない女は不幸であると納得させられたのだ。狂気の女を憐れんだり同情したりしていた自分がいかに無知であり、傲慢であったかを思い知らされ、愕然とした。あるいは『定家』。男の妄執が死後に蔦葛となって女の墓に絡みつき、女の霊はこれに閉じ込められて苦しんでいる。そこへ訪れた僧が法力によって女をいったんは解放するのだが、結局女は再び葛の中に囚えられてしまうという話である。これを私は愚かにも男の執念の強さと女の苦悩のドラマだと思っていた。ところが友枝昭世演ずる女主人公は、自由を得た後、今度は自分の意志で葛の牢獄へと戻っていくのである。驚いてテキストを読み直すと、確かに私の解釈は間違いだった。はっきりと「夜の契りの夢の中」を目指して元の場所に帰るのだと書いてある。彼女は成仏の平安よりも「互いの苦しみ離れやら」ぬ愛欲の闇を択んだのである。また『道成寺』は裏切られた女が大蛇に変身して復讐するというホラー映画のような話なのだが、友枝昭世の舞台では恐ろしい鬼女の面の下に絶望と悲しみが湛えられているのが見えてくる。すると浮かび上がってくるドラマは一変する。このような例を挙げているときりがない。
これらは近代的な心理劇とは対極にある。ギリシァ悲劇やシェイクスピアの古典劇が描くのは常識的な近代人ではないけれども、一貫した行動は合理的に理解できる。しかし能が取り上げるのは正気よりも狂気を選び、自由よりも拘束を選び、人であることよりも鬼であることを選ぶといった、まったく不合理な、けれどもおそらく私たちの精神の深層に潜んでいる衝動である。現代演劇は複雑な世界を単純な図式に整理したり、不合理な行動に心理的説明をつけたりして、観客に理解可能なものにする。さもなければ、はじめから理解を拒否して、意図的に不条理な内容を組み立てる。けれども能は理解可能な一線を超えたところに生のリアリティを見出すのだ。
中世は「物狂い」の意義を発見した時代である。それまで狂気とは神や死者などの霊が取り憑くことだとみなされていた。だがもう一つ、物思いの果てに人は別の次元に入ってしまうことがある。たとえば中世の文学者たちがもっとも尊敬したのは歌人定家であったが、その後継者を自認する正徹は「寝覚めなどに定家の歌を思い出すと物狂いになる心地がする」と言う。夢うつつのときに定家の世界に入ると狂気になるというのだ。世阿弥は『風姿花伝』で新しい形の狂気を能の「一大事」とした。それは別れれた子を尋ねる母、夫に捨てられた妻、恋人に先立たれた男などの「思ひに狂乱する物狂」である。常識人である観客には、いくら想像力を働かせても思い詰めた末の狂気など理解できるはずもない。それは理解を拒否する不条理のせいではなく、ただ私たちの理解が追いつかないのである。けれどもその姿は人の在り方のひとつの極北としてリアリティを持って立ち現れるだろう。
友枝昭世はこの狂気の域に達した思いを舞台上に現出させる。観客は理解の届かない思いの深さに茫然とし、感動する。一度このような経験をすると、もう元には戻れない。たとえばこう思うのだ。近代演劇は作家も俳優も演出家も、観客に理解できる人物像を提供することに苦心してきたが、実はそんなものを見せられたって面白くない。なぜなら「理解できる」とは「既に知っている」あるいは「知っていることをもとに想像がつく」ということなのだから。優れた芸術とは観客に未知の真実を垣間見せてくれるものである。この意味で能は現代に最も強力な芸術の一つなのである。
Flying Cabinet