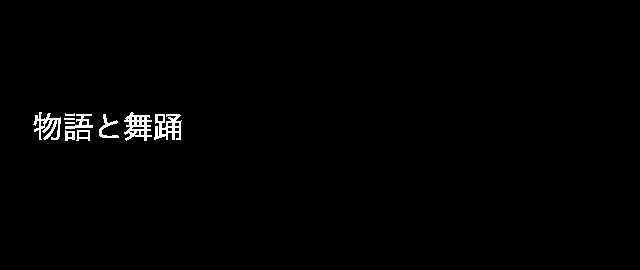五月に西洋の物語を和風に仕立てた作品が二つ公演された。一つは俳優祭の『白雪姫』(初演一九七五年)、もう一つは創作舞踊劇場の『予言』(新作)である。俳優祭はもともと歌舞伎の観客サービスだから、まじめに芝居なんかしない(玉三郎を除いて)。たとえば白雪姫が毒りんごで絶命すると観音がおごそかに登場する。観音樣といえば人助け。観客は当然、ああこれで助かるのか、と思う。ところがこの北千住観音はひとしきり踊ったあと「さして用事もあらざれば」と引っ込んでしまうのだ。おいおい助けろよ、それがお前の仕事だろう、と観客はツッコミを入れたくなる。もちろん意味なく登場した人物が「さして用事もあらざれば」と引っ込むのは伝統のギャグだが、大事な用を抱えて登場したはずのキャラクターにこういうギャグを引用させるのは、伝統のギャグそのものをネタにしたギャグであり、現代の自己批評的パロディに通ずるやり方だ。あるいは箒に乗った魔女が花道を六法で駆け抜ける。これを普通の役者がやればただのパロディだが、なにしろ飛び六法の本家である團十郎がやるのだから自己パロディになる。つまりこの舞台は歌舞伎版白雪姫などという殊勝なものではなく、ただ白雪姫というよく知られた物語をネタにして徹底的に遊んでみようというものなのだ。そのために歌舞伎という古い形式を使いながら古くさく見えないのは、自分をギャグの素材にできる自己批評性があるからだ。そのクールさは江戸の粋の精神に根ざしているのかもしれない。逆に言えば、自己を客観的に見る眼のない、まじめなだけのベタな作品は、昔風に言えば野暮ということになるだろう。
『予言』はまじめである。シェイクスピアの『マクベス』をネタにして何か別のことをやろうというのではなく、原作をほとんどそのまま舞踊劇化している。つまり悲劇的物語を身体で語ろうとしている(民衆を出したのは、ちょっと社会性も加えたかったからか)。『マクベス』の和風化には黒澤明の『蜘蛛巣城』や蜷川幸雄の演出の先例があるが、いずれも独自の世界とキャラクターを構築することで、独自の悲劇性を作り出している。しかし『予言』はどういう世界を作ろうとしたのかわからない。ただ筋書きを舞踊形式で説明しているだけのように見える。個々のキャラクターにはシェイクスピアの大きさもなければ近代演劇の複雑さもなく、ただ記号的な類型を演じているだけに見える。たしかにそれは従来の日本舞踊のやり方かもしれないが、その代わり日本舞踊は入り組んだドラマを語ろうとしてこなかったのではないか。能や日本舞踊は筋書きを単純化することで得られる普遍的な悲劇性を象徴的に表現することで深い感動を与えることに成功してきたのではないか。それから気になったのが戦闘シーン。技量の高い男性舞踊家を多勢揃えればこういうダイナミックな群舞をやりたくなるのは人情だろうが、そして日本舞踊としては迫力があると言っていいのだろうが、映画やテレビの戦闘シーンを見なれた現代人の眼にはなんとも薄っぺらい。これは日本舞踊に限らず舞踊そのものが戦場の凶暴や戦争の悲惨の直接表現には向いていないからだ。じっさいアウシュビッツや原爆をはじめ戦争を題材にした現代舞踊は多いけれど、よほどひねった角度から迫らなければたいがい失敗している。これは表現のリアルさの問題ではない。文字だけの文学や講談師等の語りのほうがよほど戦争のイメージを伝えることができる。表現メディアの性質の問題なのである。とにかく話の筋さえ伝わればいいや、というのでは日本舞踊化した意義がない。
シェイクスピアを日本舞踊でという意欲は貴重なものだ。しかし複雑な物語を素材にするには、まず日本舞踊に何ができて何ができないかを自覚しておく必要があるだろう。その上で、得意な土俵に引き込むか、新しい手法を開発する必要があるだろう。つまりこういう場合こそ自己批評の目がなければならない。まじめだけでは役者の座興にも勝てないのである。
Flying Cabinet