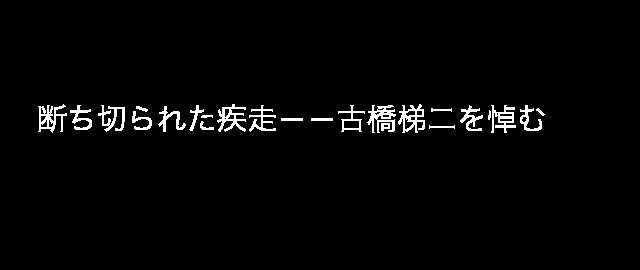十月末のある夜遅く電話が鳴り、古橋悌二の訃報を聞いた。深夜ではあったが、私は切れた受話器を下ろさぬまま友人の番号を押し、ダムタイプの演出家の死を伝え、しばらく話しこんだ。彼女は私との電話を切ったあとも眠ることができず、次々と知人に電話をかけ、最後の人とは一時間以上話しこんだという。その人は、既に古橋の死を聞いて衝撃をうけ、話し相手を探していたところだったそうだ。おそらくその夜、彼の訃報は日本中の電話線を波紋のようにひろがり、至るところで細い銅線が眠れぬ人々を結び合わせていたことだろう。
古橋の夭折が私たちにとって痛恨であったのは、近作『S/N』によって驚くべき舞台を創造したばかりであったからだ。日本はようやくピナ・バウシュやフォーサイスに匹敵する革命的芸術家を得たというときめきがあったからだ。『S/N』の舞台では、疾走してきたダンサーたちが突然立ち止まり、直立不動のまま後ろに倒れ、崖から落ちるように舞台の向こうに消えてゆく光景が繰り返される。ちょうどそんなふうに、古橋は消えた。大観衆を前にテープを切り、月桂樹の冠を受けるところを見たかったという思いが、私たちにはある。もっとも、古橋自身は、そんなことはどうでもよかったに違いない。彼の直面していた問題は、はるかに大きく、切実なものだった。
ダムタイプは一九八四年、京都市立芸術大学美術科の学生を中心として設立され、先行する何者にも似ていない舞台は数年のうちに国際的評価を得た。とりわけキッチュな社会の断片をコンピュータを用いて息詰まる展開の中に構成した『pH』(一九九〇)は、ポストモダンと呼ばれた八十年代を象徴するパフォーマンスとなった。だが『S/N』はまったくちがっていた。それは性(セクシュアリティ)とエイズを主題とする。しかも古橋は、自分が同性愛者であり、HIV感染者であることを公表したのである。作品はもはや電子映像のような非現実の世界ではなく、現実と地続きのものとなった。
八六年、古橋はニューヨークでエイズを主題とするイベント『セックス・アンド・ダンス』を見ている。彼の文を引こう。「最後に、ある有名なゲイ・ポルノのスターが出てきて、彼がいつも四二丁目の劇場でやっているようにストリップをはじめた。・・その美しい容姿とたくましい肉体はゲイだけではなく女性客をも魅了するものだった。が、彼は全裸になる直前にいきなり自分がHIVに感染していることを公表した。それ以降のストリップで観客は最も残酷な時間を体験した。・・我々は呆然と涙を流した。彼に対する憐愍の情からではない。全裸の彼にエロスを感じることすら許されなくなってしまった自分に対して泣いたのだ」(「芸術は可能か?」へるめす、九三年五月号)
九二年、古橋は友人たちにHIV感染を告げ、これを契機に『S/N』は生まれた。この作品は明確なメッセージを持つ。国籍、人種、職業の境界。同性愛と異性愛、HIVポジティヴとネガティヴ、障害者と健常者の間の境界。人為的に作られたこれら一切の境界線を破棄せよということである。この素朴とも見えるほど急進的なメッセージを、彼はテクノロジーを駆使した疾走する表現と、実生活を負った出演者による不器用なほどの対話によって提示した。普通の演劇も普通のダンスもここにはなかった。けれども舞台上で女装の身支度を整えた古橋が女王のように歌い始めたとき、何人かの観客は呆然と涙を流したのである。
私はどれほど感動した舞台も日が経つにつれ忘れていくのに、この作品だけは日を追って記憶が鮮明になっていった。たぶんそれは私だけではなかった。なぜなら、時が経つにつれて『S/N』について知人と話しあうことが多くなったからだ。これは初めての経験だった。いったい古橋は何をしたのか? たぶん何か革命的なことをしたのだ。それが何かを知るためにはさらに彼の作品を見なければならない。しかし、見ることはできない。
Flying Cabinet