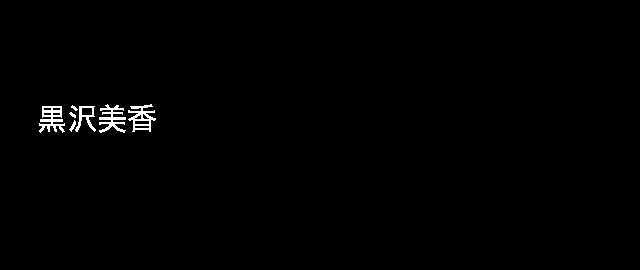それは忘れがたい体験だった。
舞台に三人の女性が立っていた。右端の女性の衣装は上半身がシースルーで、豊かな胸がはっきり見える。三人は微動だにしない。男の客は右の女性を見てればいいじゃないかと言うかもしれないが、あんなものは一分も見れば退屈する。ただ時間が過ぎてゆく。私はジョン・ケージの『四分三三秒』を思い出した。このまま最後まで何もないんじゃないか。そのときだ。実に見事なタイミングなのだが、左の女性の手がかすかに動き始めたのである。ゆっくりと、ほんとうにゆっくりと変化が進む。左と中央の女性は手を突き出し頭を抱えては戻るという動作を繰り返す。右の女性は手をだらりと下げたまま、小刻みに始めた貧乏揺すりを次第に大きくしてゆく。ついには胸が大きく揺れるようになる。シースルーはこれを見せるためだったのである。確かに単調である。しかし退屈ではない。不思議な時間が流れだすのだ。遠くから洩れてくるかすかなモダン・ジャズ。すきまから差し込むような黄色くかぼそい照明。古い寺院にいるような穏やかな気分。三人のダンサーは何物も表現せず、内側にトリップしている。単調な動きの中に自足し、自壊してゆくだけである。だがこの三人が三尊仏のように見えはじめる。永遠にこのままでもいい、と思いはじめる。そして私はダンスのまったく新しい形を経験していることに気がついた。これは見ることが大事なのではない。傍に居ることが大事なのだ。じっと見つめていなくともよい。ぼんやりと他のことを考えていてもかまわない。だがふと目を戻すと、そこに同じように三人の女性像がかすかな音と光の中でゆっくりと動いている。それが私を安堵させる。そして豪奢な時間の中にいるのを感じる。いったい私はトリップから我に帰ったのだろうか、それとも日常の世界を出てトリップに入ったのだろうか。多分三人のトリップが私に感染しているのだが、このトリップは異様に醒めている。この時間経験はほとんど感動的でさえあった。一九九一年一一月、バニョレ国際振付賞日本国内推薦会の最後の作品、黒沢美香の『零度のダンス』である。バニョレは彼女を招くことに決定した。 黒沢は一九六〇年代から優れたダンサーとして国内で数々の賞をさらっていた。ここ数年は実験的な作品を定期的に送り出し、先鋭な振付家としての地位を固めていた。そしてついに世界が彼女を評価する時が来た。少なくとも私はそう思った。なぜなら、西欧ではアヴァンギャルドの破壊、ポストモダンの解体を経て、九〇年代の芸術家たちの試みは再び新しい様式の創造へと向かっているようだが、『零度のダンス』はまさに比類のない時空の形式を創りだしたという点で、模範的な成果であったからだ。
黒沢はこの作品を携えて翌年バニョレに臨んだ。しかし聞くところでは、あの奇跡とも思える時間の再現には失敗したらしい。あまりにも繊細な作品は、ほんの僅かな手違いが全体を台無しにしてしまうことがあるものだ。そして最近の黒沢は、逆の方向に走っているように見える。一つの世界を生み出すことよりも、破壊することを。透明で凝縮した時空よりも、混乱し拡散した場所を。緊張よりも弛緩を。彼女は昔のアヴァンギャルドからもう一度やり直そうとしているのかもしれない。それを他人がとやかく言うことはできない。けれども、と私は思うのだ。あのときの時間がもしバニョレで再現されていたら、黒沢美香の名はいまごろ世界でも数少ない創造的舞踊家として知られていたであろうと。
Flying Cabinet