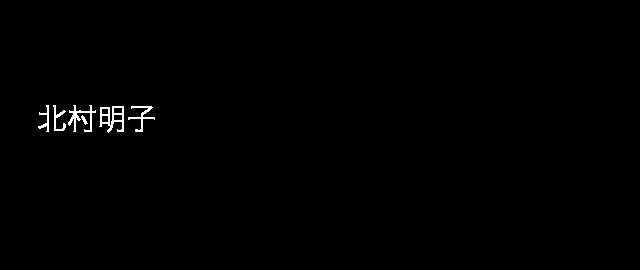北村明子はまだ二三才である。評価を下すのは早すぎるかもしれない。しかし彼女は早稲田大学入学と同時にダンス・グループ『Leni-Basso』を旗揚げし、この五年の間に既にかなりの作品を発表してきた。とりわけこの二年ほどは、迷走するようにまったく違ったスタイルに挑戦しながら、しかも高い水準を確保してきた。だから少なくともこう言うことは許されるだろう。北村明子には才能がある。
二十世紀芸術にとって六十年代が革命と前衛の季節であったとすれば、一九七〇年に生まれた北村は文字通りのポスト前衛世代である。この世代の一つの特徴は、二〇世紀芸術を風靡した「前衛とキッチュ」という二分法、即ち「エリートのための高級な前衛芸術」と「大衆のための低級な商業芸術」という差別意識から解放されていることだ。彼女が作品を創りはじめるにあたって、まず面白いものを目指したのは当然のことである。九二年の『RUSTY ICE 』はリズムに乗った小気味よい動きが対位法的に展開し、このままブロードウェイに持っていきたいと思うほど楽しいものだった。振付の出来ばえは、マイケル・ジャクソンの『スリラー』にも負けない。北村は二一歳にして既にジャズダンスのマイスターであった。しかし大衆の好きなブロードウェイへ現代舞踊愛好家があまり行かないのはなぜか。明確なリズムに乗り、型にはまった動きを繰り返すショーダンスは、予想を裏切られ、新しい世界を覗くという快感がないからである。九三年、『MELTING INTO MY DOUBLE』で北村はまったく違ったスタイルを見せる。もはや観客は、前作のように気持ちよくダンスに同化することはできない。時間は、スローモーションによる緊張の持続と、突然の痙攣によるその切断によって構成される。音楽は拍子をとるためのものではなく、背景音のように扱われる。というより、音と光と美術装置はダンスから自立して作品空間の要素となる。北村の巧みな構成・演出によって、これもまた間違いなく「面白い」作品であった。そして九四年、バニョレ国際振付賞東京プラットホームに選ばれて登場した作品は、三たび作風を一変させていた。この『Whenever I was watching you, You stared at yourself 』はまるでヌーヴェル・ダンスを見るようだった。振付コンクールという性格上、バニョレ側からさざまな制約を加えられたこともあったようだが、焦点は身体の動きに置かれた。ダンサーたちは緩慢な動作と一瞬の激しい動きとを苦しげに反復し、何度もよろめいては転倒した。観客の同化を拒否する禁欲的な所作が、明滅し、断続し、重複する。振付はかなり緻密であったが、彼女がそこに立ちのぼらせようとしていた世界は(演出上の制約やダンサーの力量の問題もあったろうが)はっきり見えたとは言いがたい。だが突然の試みにしては水準は高く、バニョレ行きに選ばれた作品に比べても遜色のないものだった。
北村が目指しているものは、額縁舞台で身体だけに頼ったダンスを見せることではない。その意味で『Whenever・・・』は彼女の本領ではない。だがこの寄り道は無駄ではなく、自分のやるべきことについて確信を深めたようだ。この夏北村は新作を問う。聞くところではそれは、舞台と客席との落差を取り払い、音や光や映像が劇場空間を満たし、ダンスと他の要素とが交錯し混淆するようなものであるらしい。五感の全てに演出を仕掛けてゆく北村の作品は、芸術の境界が曖昧になり、ダンスの定義が書き直されようとしている現代の、一つの方向を示すものだろう。『Leni-Basso』とは、レニ・リーフェンシュタールの再来という意味である。
Flying Cabinet